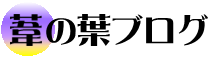本号ではタイトルにもありますように、デジタル無策が実体経済に及ぼす影響について考察しますが、このまま無策が続けば、日本の経済の屋台骨であった製造業にまで影響が及ぶという近未来の予測までなされています。この状況を経済界はどのように認識しているのかも合わせて検証しています。選挙絡みの記事では、維新の会吉村会長が責任を放棄する、万博建設費の踏み倒し詐欺事件もご紹介。(アイキャッチ画像はMS Bingで作成)
目次
1.デジタル赤字が製造業にまで拡大
参院選、投票日も間近に迫ってきました。新しい政党も加わり、賑やかな選挙戦が展開されていますが、物価高が続く中、選挙戦の最大の争点はズバリ経済問題。
その対応策としては減税か給付か、あるいは両方か、各党の対応は分かれていますが、同時に賃上げや経済成長を図ることは不可欠だとの主張もなされています。どれももっともな主張のように思われますが、経済問題の核心は、ズバリIT/AI人材の育成いかんにかかっているといっても過言ではありません。現在は外国人に頼っているデジタル人材を、国内でまかなえるように転換することは、経済成長にも賃上げにも必須の条件です。
以下の記事は、経産省が、日本のデジタル市場における対外支払い超過である「デジタル赤字」を分析した結果を紹介したものですが、デジタル赤字がやがて日本の製造業そのものを赤字に陥らせる可能があるとの、恐ろしい近未来予測も示されています。
「隠れデジタル赤字」が日本の危機を映す、最悪シナリオはソフトの弱さで製造業も赤字
玄 忠雄 日経クロステック/日経コンピュータ 2025.07.07
製造業は日本経済の屋台骨として、順位は後退したとはいえ、日本を世界4位の経済大国の位置に留め置いてくれているわけですが、その製造業が赤字になれば4位どころか、もっと下位に転落し、日本経済は悲惨な状況に陥るおそれがあるとのことです。
なぜこんな恐怖の予測がなされるのかといえば、製造業もデジタル技術の塊になっているからですが、今後ますますこの傾向は強くなります。
にもかかわらず、デジタル対応力が極度に低い日本は、自前でデジタル技術やデジタル製品(ソフトウェア)の開発できず、海外に依存する割合が非常に高いので、車なら車で、海外から輸入した、高額なデジタル技術やソフト類に依存せざるを得ず、その支払いで赤字にならざるをえなくなるということです。
デジタル収支の赤字といえば、われわれ一般ユーザーがネット上で日々利用するGAFAM(Google、Apple、Facebook(現Meta)、Amazon、Microsoft)などのアメリカの大テック企業に起因するとの思い込みが強いかと思いますが、デジタル赤字の由来は、一般ユーザーにのみとどまるものではなく、製造業にまで及んでいるということです。
生成AIが一気に普及した現在では、GAFAM以外のOpenAIなどの新興のテック企業も加わってきます。台湾からの半導体輸入は、熊本にTSMCが進出しましたので輸入は減少するとは思われますが、技術料は当然台湾に流れます。さらには、世界無敵と思われたアメリカを猛追している中国のテック企業の技術についても、購入する必要も出てくる可能性も否定はできません。また、派手ではないながらも、欧州にも優秀なテック企業はいくつも存在しています。
となると、日本のデジタル赤字は今後ますます拡大することはあっても縮小する可能性は低いとの、悲劇的な予測まで出てくるおそれもゼロではありません。
おまけに、Google依存のデジタル庁の登場で、日本国のデジタル赤字は膨張する一方。しかも、デジタル庁は登録す国民の個人情報をさらに拡大する方針です。となると。登録する情報量が増えれば増えるほど、日本政府がGoogleに支払う費用は膨らみますので、日本のデジタル赤字は膨張の一途をたどります。こんな役所の存続を許してもいいのでしょうか。
という恐ろしい未来予測にまでわれわれ読者をいざなった上記の記事は、これまで、どんな経済分析にもなかった新たな視点からなされたかなり衝撃的なものでした。しかし、この衝撃的な結果は、デジタル収支の計測法を従来よりも詳細な手法に変えて、かなり実態に近い計測をした結果によるものだという。ということは、日本のデジタル赤字はこれまで発表されてきた額よりも大きかったということです。
わたしはこの記事を読んで、かねてからの疑問が氷解しました。というのは、これまで日本のデジタル赤字は5兆円ぐらいだと発表されてきましたが、デジタル赤字はこんな小さいのかと不信を抱いていたからです。素人ながらの実感では、日本のデジタル赤字はもっと大きいはずだとの疑念をずっと抱いていました。
今回は計測をより詳細にして、取りこぼしを極力なくすように計測したとのことですが、おそらくそれでもカバーできないところもあるはずです。
デジタル技術は、人の暮らしのありとあらゆる領域を覆い尽くすほどに使われていることは、当サイトでも繰り返し繰り返し伝えてきました。
PCやスマホに始まり、テレビや冷蔵庫やラジオ、エアコン、電灯、ガステーブル、レンジ、子どもおもちゃ、自転車、門柱や庭の照明灯、お風呂、ドアの鍵などなど、日々の暮らしの中で目につくものほぼ全てにデジタル技術が使われているといっても過言ではありません。
ごく稀な例としては、スマートハウスになれば、家そのものがデジタル化されていますし、スマートシティともなれば町全体がデジタル化されています。農業、漁業でもデジタル技術は使われています。
車はいうまでもありませんが、電線や信号機にも使われています。電車や飛行機や船、ロケットなどなど、空間を広げてみても、デジタルと無縁な空間はないといっても過言ではありません。医療分野でもデジタル化が急速に進んでいます。
例示もれはまだまだあるかと思いますが、デジタルとは無縁な空間、場所、モノはないほどに、暮らしの隅々にまでデジタル技術が浸透している現状を考えますと、その利用実態を正確に把握することは、今回の改正された計測法でも全貌を把握することは無理だろうと思います。
しかし諸々の政策立案に際しては、デジタル技術の利用実態は極力正確に把握する必要があります。そこで補助手段として、デジタル技術は人の営みの隅々にまで及ぶほどに浸透普及している事実を認識することで、計測がカバーできない部分を補うべきではないか。つまり、計測結果が示したデジタル赤字よりも、日本のデジタル赤字はもっと大きいとの認識を持つ必要があるということです。
正確な現状把握なしには、有効な政策など考えようもないからです。AI敗戦という、今現在に至る結果がそれを如実に示しています。
2.賃上げが物価高騰の原因?
実はもう一つ、以下の恐ろしい経済分析結果を目にしました。
東洋経済オンライン 2025/7/6
日本を破滅させる「賃金と物価の悪循環」という病
野口悠紀雄
参院選たけなわの今、与野党はもとより、新党各党の選挙公約、主張に非常に大きな打撃を与えずにはいないほどの内容で、選挙活動そのものにブレーキをかきかねないことから、ご紹介するのは選挙後にしようかとも考えておりました。
しかし、IT/AI敗戦下にある日本の実態を解明するためには、他に代替不可能なほどの貴重な分析資料ですので、選挙渦中にあえて取り上げることにしました。
著名な経済学者である野口悠紀雄氏の上記分析は他に類例のないものだと思われますが、その特異点は、「日本の物価高騰の原因は、2023年から大きく変化した。」と、2023年を起点に置いたことにあります。
2023年以前の物価高は海外要因(ガソリンなどの輸入品の値上げ)によるものであったのに対して、2023年以降は、国内要因による物価高だということが、データーを使って示されています。
特に最近は「輸入物価が10%下落なのに消費者物価は3.7%も上昇」。明らかに国内要因による物価高騰ですが、問題はその国内要因です。野口氏は、2023年頃から始まった大幅な賃上げによるものだとの衝撃的な事実を、データーを使って明らかにしています。
確かに、2023年頃から政府主導にも近い形で賃上げが行われてきました。以降、今年の春闘まで大企業を中心にかなり大幅な賃上げが行なわれてきました。しかし野口氏によると、今の日本では、賃上げすればするほど物価高騰を招くという、恐ろしい負のスパイラルに見舞われているという。
なぜなのか。その理由とは、日本の労働生産性が低いからだという。コロナ禍ではGDPが低下したことから相対的に労働生産性は高くなったが、これは実態とは無関係な相対的な数値上の変化にすぎず、実態としては、日本の労働生産性は長期にわたって低下の一途をたどっているという。
そんな中での大幅賃上げ。その結果急騰した労働コストを、企業は販売価格に上乗せしており、それが物価高騰の原因だと、野口氏はデータを使って分析しています。つまり今の日本は、賃上げをすればするほど物価高騰を招くという、恐ろしい状況下に置かれているらしい。
株主還元や経営者への報酬はどんどん上げる一方、膨張し続ける内部留保は使わずに価格に転嫁。しかし中小企業は同じような動きはできません。結果、格差は広がるばかり。これが物価高騰下の日本の現状らしい。
しかしわれわれ一般人が、身勝手な経営者をいくら批判しても株主が認めれば全てOKですので、経営者や企業をいくら批判しても問題は解決しません。また、野口氏の分析も、経営者を喜ばせるためのものではないかとの批判を招く側面もなきにしもあらずですが、賃上げ分は価格に上乗せされていることは事実のようなので、賃上げ実現で問題は解決するとの単純な思考に浮かれている政府や経済界の妄想を突き破るためにも、まずは野口氏の分析結果に焦点を当てることにします。
ではどうすれば物価が下がるのか、答えは明白。労働生産性を上げること。これに尽きますが、労働生産性とは、単位当たり(労働者1人当たり、あるいは、労働1時間当たり)で生み出される成果、付加価値を表す数値のことですので(BIZ HINT)、労働の現場において、効率よくどれだけの付加価値を生み出せるのかが最重要ポイントになります。
その具体的な方策は、上記記事には含まれていませんが、誰も即座に思いつくのがIT/AI技術の活用だと思います。実際、小泉政権時にも労働生産性を上げるために、IT(当時はまだAIは未登場)の活用が賑々しく喧伝されていましたが、政府(小泉政権)は掛け声だけで、IT活用の具体策は何ら示さぬまま、結果としてIT/AI敗戦への道筋をつけただけでした。
では何が問題だったのか。解決策はあるのか。多々湧き出す疑問に対してはわたしのIT/AI論評と接続しつつ、その方策を探ることにいたしますが、その前に、労働生産性向上のカギを握る、日本の経済界の現状認識について確認することにします。
3.十倉雅和前経団連会長の時代錯誤
十倉前経団連会長は、会長退任後の会見で、鳴りを潜めていた道州制の復活を提唱するという時代錯誤な発言をしています。今の日本には、そんなことをやっているヒマはないといいたい。
道州制が最初に登場したのは20数年前、小泉政権の頃でした。この時期2000年前後の頃は、統治機構の大改革との触れ込みで、国公立大学の大改編をも含む、省庁の大改革が行われ、科学立国日本を陰で支えてきた科学技術庁が解体されるという大惨事が発生。この大惨事の影響は現在にも及んでいます。
この省庁大改革は財務省が陰の首謀者だとされていますが、この大改革では、税金のムダが削減されるどころか、大改編に伴う巨額の浪費が国の借金を膨張させただけでした。
この省庁の大改編が終わった頃、統治機構の地方版とばかり、今度は平成の大合併という地方自治体の合併が実施されました。しかしこの平成の大合併も、巨額の税金が浪費されただけで、地方自治の効率化が実現できたのかといえば、大合併で浪費した税金が国の借金として上乗せされただけで、成果はゼロ。地方はただ不便になって過疎化が進んだだけ。
この間、道州制導入に最も熱心だったのは維新の会で、一貫して道州制の導入を主張し続けてきました。マスコミもあおるような大きな扱いで、維新の会の道州制を報道してきました。
しかし維新の会は道州制の実現はすぐには難しいと判断したのか、大阪だけで実施可能な大阪都構想へと軸足を移し。道州制そのものへの動きはひとまず収まり、静かになったのですが、20年余経った今、十倉氏が再び再燃させました。維新の会も当然のことながら道州制への意思は変わらず、十倉氏の提言に百万力を得たと喜んでいるはずで、十倉会長の発言後、吉村氏も道州制を口にするようになりました。
道州制の反時代性とITの多重下請け構造
しかしわたしは、道州制には一貫して反対してきました。今の時代は、物理的に組織や地方自治体の組み合わせを変えたり、吸収合併させたりしただけで難問が解決できるような牧歌的な時代ではないからです。
この時代の変化を象徴的に体現しているのが、IT技術、デジタル技術です。人類史を画するこの新技術を、国家としていかに受け入れ、国家運営に活かすことができるか。この大難問に過たず対応するためには、国の総力を挙げて取り組む必要があります。道州制などで騒いでいる場合ではないのです。
しかし日本の政治家は誰一人として、この技術の人類史を画する特異性を認識できずに、自力でこの技術を受け入れるための体制を構築できぬまま、現在にまで至っているというのが偽らざる実情です。特に歴代政権の責任は重大です。
ただ、省庁再編前までは、官僚レベルではデジタル化への対応は多少なりとも進みつつありました。例えば、体験的に認識しうる出版業界の例でいうならば、1990年代末(省庁改変前)までは、電子書籍などのデジタル技術の導入に向けた法整備がなされ始めていました。
ところが、大々的な省庁大改編が始まると、デジタル化に向けた動きはピタリと止まってしまいました。問題の軽重の認識が完全に逆転しており、デジタルどころではない。省庁改編こそが日本の命とばかりの狂奔が、マスコミも一体になって日本中を覆いました。
この狂奔が続く中、デジタル化の動きはAmazonの上陸まで休眠状態でしたが、休眠中に突如大巨人の襲来。しかしこの巨人の襲来を受けても、科学技術庁も消されてしまった中では、すぐには動けないような悲惨な状況がしばらく続きました。
という、ごく限られた体験的な振り返りからだけでも、組織の改編が何をもたらすかは、説明無用でしょう。
ちょうど同じ頃、日本の学術研究分野でも類似の現象が発生しています。中国がIT研究で目覚ましい活躍を見せ始めた頃のことです。
中国の情報学研究機関のトップが、日本に対して、次のような評価を口にしていました。情報学の研究において中国は、1990年台末頃までの日本からは、さまざまなものを学ばせてもらったが、2000年台以降に入ってからは、学ぶべきものはほとんどなくなったと。
ここまではっきりと口にするのは珍しいですが、大改編がIT化の普及を阻止するために使われたというわたしの認識にピタリとはまる批評でしたので、今も鮮明に覚えています。また、政府ではなく民間ではあるものの、韓国人とは異なり、中国人は日本から得たものがあれば、それとして認めるのだなあとの感想もあり、この批評はよく覚えています。
実際、この批評通りに1990年台末頃からは、国公立大学の大改編と省庁の大改革が行われて、それまでの事業の継続や研究の継続も停止や停滞を余儀なくされる状況が続いていた時期に当たります。特に、ほとんど蓄積のない新興のIT分野では、物理的な停滞要因から受けたダメージはかなり大きかったのではないか。それが、中国人の専門家から見ても、2000年台以降の日本におけるIT研究の停滞という、シビアな評価につながったのではないかと思われます。
また、度重なる組織の改編はIT企業にも甚大な影響を与えています。国の組織、省庁の構成がガラリと変わりましたので、この改編に伴うシステム改編需要が激増します。関連する民間企業や組織や学校等にまで及び、システム改編需要は何年にも及んだはずです。投ぜられた税金の額は莫大ですが、受注したIT企業にとっては、これ以上ない最優良な受注。一気に売り上げ増につながります。また、引っ越し関連企業にとっても、最優良な受注でした。
省庁改編に伴う巨額の国費投入で、国民に恩恵は届かないものの、企業は潤っていました。
さらには同じ頃に、平成の大合併も始まりましたが、こちらは1999年(平成11年)から2010年(平成22年)までの11年間の長期にわたって実施されたという。時期は重なっていますが、両者は統一的なビジョンに基づいて実施されたものではなく、それぞれバラバラ。多分、思い付きでしょう。
この平成の大合併でも、システム改編作業が必要となり、IT企業の売り上げはさらに増加。ここでも巨額の国費投入で、国民には恩恵は届かないものの、企業は潤っていました。
今の時代、組織を動かすと、必ずコンピュータシステムの改編作業が発生します。それが国家機関となると、システム改編業務に関わる経費や労力は莫大なものになります。
日本は官も民もIT技術者は内部では抱えずに外部委託ですので、官僚の皆さんや地方自治体の職員の皆さんは、システム構築はもとより改編作業はノータッチ。日常的な管理も外部の業者任せ。唯一例外的に鳥取県は、たった3人の技術者だけで独自の住民情報の管理すステムを構築したとのことが、かなり前の東洋経済オンラインで紹介されていました。
という例外はあるものの、国や自治体からシステム改編を受注したIT企業は自社では実際の作業はせずに下請け企業に丸投げ。コロナ禍対応渦中に、国のIT業務も下請け、孫請け、ひ孫請け・・・という、IT業務における多重下請け構造が明らかになりましたが、今もこの構造には変化はありません。IT/AI専門の役所であるデジタル庁ですら多重下請けを採用していたぐらいです。
理由の第一は人材不足ですが、人材育成がなされぬまま、多重下請け構造が常態化してしまうと、この構造を変えることは非常に難しいということです。中でも問題なのは、この多重下請け構造下では日本人技術者が占める割合は少なく、外国人技術者への依存が圧倒的な割合を占めていることです。つまり、実際のプログラミングなどの業務は、外国人が請け負っているのが現実だということです。
巨大なシステム改編特需が生まれ、巨額の税金が投じられた国家プロジェクトであっても、受注した日本のIT企業は巨額の収益を手にはするものの、労働者であるIT技術者は大半が外国人ですので、一般労働以上に高額が支給されているはずの給与・報酬は外個人労働者(技術者)に支給され、そうした業務に就く技術を持たない日本人労働者には、この国家プロジェクトによる特需の恩恵は全く及ばないというのが、多重下請け構造の特性です。
企業が潤っても国民には実感がないというのは、日本人労働者はこの特需に参加することすらできないからです。IT特需による経済効果は、直接的には大半の日本国民には恩恵が及ばぬ、中身が空洞化した歪なものだということです。空洞化した部分は外国人技術者の所得になっているわけです。企業が潤ったても国民の大半は低賃金にあえぐというのは、歴代政権によるIT無策の結果によるものでした。
しかし、IT業務の多重下請け構造の問題はこれだけではありません。ITシステムは、政府にとっても企業にとっても、他の様々な組織や団体にとっても、非常に重要な情報を保管管理する心臓部であり、頭脳の役目も果たす最重要な組織の中枢部となっています。
その中枢部の構築を外国人に委ねることは、国とっても企業にとっても非常にリスキーな事態です。仮に日本人が監督してチェックするとしても、ひ孫請けなどの下層下請けの作業までチェックすることは物理的に不可能なはず。
と考えると、IT業務を安易に外国人技術者に委託することの危険性にも気がつくはずですが、日本は、世界的に見ても唯一例外的に、官民ともに外部委託が標準になっています。海外では先進国はもとより、ほとんどの国が内製、政府や企業が自前の技術者を雇用しています。日本以外の国々は、IT技術の特異性と情報管理の重要性を認識しているからです。官民ともに、平気で外部委託している国は日本だけです。
外部委託でも、社会全体としては必要最小限度のデジタル化は実現していますので、表面的には問題なく全て処理されているように見えますが、外部委託では、デジタル技術を創造的に発展させる機会は生まれません。自分で手を動かさなければ、デジタル技術を使った新しい製品やサービスなど生まれようもありませんし、委託業者にすると、受託した業務を確実にこなすことが全てであり、それ以外の仕事などするはずもなければ、できるはずもありません。
日本からはデジタル技術を使った新規の技術や製品(ソフトウェア)などほとんどないというのも、人材不足に加え、外部委託が標準化されているという、世界的に見てもきわめて珍しい経済構造にも起因しているはずです。
20年後に再燃した道州制推進論
現在は、生成AIを使えば一瞬でプログラミングコードが生成されるとはいえ、生成AIにコードを書かせるにもプログラミングの知識は必須です。義務教育終了までにはプログラミングの基礎知識は習得すべきですが、日本では今現在もその最低の教育さえ受けぬまま子供たちは社会に放り出されています。
今再びの道州制提唱は、こんな状態を放置したまま、またもや統治機構を物理的に動かそうという企みです。20数年前の省庁改変や平成の大合併という統治機構の改編時にも、それまで徐々にながら動き始めていたIT化への流れが、これらの改編事業がピタリと止まり、その後の日本のIT化、デジタル化の致命的な遅れの端緒となりました。
つい最近再燃した道州制への動きがさらに大きくなれば、ITが生成AIにまで進化した現在の社会的対応を決定的に遅らせる契機になるはずです。
さらに、統治機構を物理的に動かすとなると、またもや官民すべてにおいて、公的機関のシステムの改編が必要になりますが、デジタル庁ができたとはいえ、今のデジタル庁は信用できませんので、その改編業務も多層下請けに丸投げということになります。
そんなことばかり繰り返していいのですか。IT企業にとっては確実に収益が上がりますが、こんなシステム改編作業を繰り返しても、AI技術の進展には全くつながりません。
わたしは20数年前の省庁改変や平成の大合併の時も、道州制も含めて、こんな類型的なシステム改編事業ばかり繰り返しているだけでは、世界最先端のITの潮流に触れる機会も持てず、取り残されるだけだと批判しました。企業としては類型的な仕事をするだけで、確実に国から巨額の支払いを受けますので、外に目を向ける必要もなければ、その余裕もないという状況に置かれます。これは日本企業にとっては、むしろ不幸なことだと思い、批判しました。
令和になっても、またもや同じ光景が繰り返されるとしたならば、日本にとって、これ以上の不幸はありません。
20数年前、日本が省庁改編や平成の大合併を繰り返していた頃、韓国ではデジタル化によって統治機構の大改革を実行したと、日本に進出している韓国のIT企業の社長さんが語っていました。おそらくこの韓国企業は、日本の公的機関のシステム改編業務を受注していたのだろうと思います。
今日本には韓国のみならず、中国、インド、ベトナムなどの海外のIT企業が進出していますが、日本政府は、日本ではなく、海外でIT人材を確保するために、特に東南アジア各国に人材育成費用を助成してきています。
助成を受けた各国では、無料でIT人材を育成して日本に送り込んでいます。なぜ、まずは日本人のIT技術者育成のために税金を投じないのでしょうか。日本がデジタル助成した国の一つインドネシアも、日本でのデジタル受注を狙っていますん。
選挙でも問題になっている就職氷河期世代に、IT/AI技術を無料で学べる機会を提供すべきであったのではないですか。またひきもりの若者も増える一方。
就職氷河期世代を役所に有期雇用する施策は実施されましたが、いかにもその場しのぎ的な政策で、就職氷河期世代の不安定な状況の解消には全く何の役にも立っていませんね。それよりも、海外で補助金を出してまでIT人材育成をする前、なぜ、就職の機会を手にすることのできなかった就職氷河期世代の方々にプログラミングを学ぶ機会を提供しなかったのか、全く理解できません。
3か月か半年ほど専門学校に通えば、ほぼ誰もが基礎的な知識やスキルはマスターできるはずです。あるいは、オンラインでもプログラミングなどのIT技術の習得は十分に可能です。むしろオンラインの方が相性はいいはずなので、人と会うのが苦手な引きこもりの方々も、デジタル技術の面白さに気づけば、IT/AI技術者としての道も開ける可能性はあるはずです。
NHK第2で月に1回ですが(なんでたった月1回なのか?)、引きこもりの方々を対象にした「ひきこもりラジオ」という番組が放送されていますが、引きこもりでない人間にとっても心癒される番組です。’
ラジオは顔が見えないので、何十年も引きこもっている人でも投稿されていますが、誰もが人と会うのが怖いといいながらも、誰かとのつながりを求めています。ごく稀ですが、このラジオへの投稿(他者との交流)がきっかけで仕事を始めたという人もいました。
無理強いは禁物ですが、引きこもりの方々も、可能ならば現状から脱したいという潜在的な欲求は持っておられるように思います。そういう方々が、デジタル技術の面白さに気づく機会に遭うことができれば、世界を変えるきっかけになる可能性もゼロではありません。
数十万人にもいる引きこもりの方々にも、プログラミングはゼロからの学びも十分に可能だと思います。
引きこもりや就職氷河期などで、持続的な仕事に就けなかった人々も、プログラミングの基礎をマスターして、実際に仕事をこなしていると、生成AIという最新形の技術についても学ぶ機会も出てくるはずです。
日本政府のIT/AI政策は、こうした不運に見舞われた日本人を放置したまま海外での人材育成に税金を投じるもので、余りにも不可解です。歴代政権に強い影響力を発揮してきた経済界からも適切な提言がなされてこなかったことは、今現在の状況が雄弁に物語っています。
政治家も経済界も現下の状況の深刻さをほとんど理解していません。経済界では、元経団連の会長をしていた日立製作所の中西会長は、事あるごとにIT、ITと口にされていたそうですが、中西氏は70を超えたばかりの若さで任期途中で急逝されました。後を継ぐ人は出てこないようです。それどころか、この無策の状態を放置したまま道州制とは、時代錯誤も甚だしいといわざるをえません。
維新の会は20数年前と同様今回もまた、道州制導入を騒々しく喧伝し、日本のデジタル対応の遅れを挽回しようとする動きを止めることを、隠された任務にしているのではないか。そんな勘ぐりさえしたくなります。
なお、日本が取るべき具体的な方策については、次号に続きます。
4.参院選2025
投票日の20日が迫ってきていますが、わざわざ3連休の中日を選ぶとは、投票率を下げて組織票を握っている自民党に有利になるようにとの、魂胆が丸見え。政策以前に、投票日の設定だけで石破政権に対する印象を悪くしていますね。
この投票日の設定が災いしたのか、選挙公報がまだ届いていません。投票日公表が遅れたことと、印刷所もまさか連休中に投票日が設定されるとはゆめ思わず、おそらく連休後になるだろうと考えていたはずで、受け入れ態勢が整っていなかったのではないかと思われます。期日前投票には、間に合わないケースも多いのでは。石破政権にとっては、それも計算の上だったのかもしれませんが、思惑通りに運ぶのかどうかは疑問です。
鶴保参院議員の発言の真相
「運のいいことに能登に地震があった」という、鶴保議員の異常な発言に日本中が驚愕に襲われましたが、この発言の異常さは、うっかり口がすべったという類のものではなく、政策を解説する中でなされた確信的な発言であった点にあります。
鶴保氏の音声を聞くと、おそらく地方創生策の一つだと思われる、二地域居住推進策について解説する中で、地震に見舞われた能登を例示してこの政策の有効性を示そうとしていましたね。つまりうっかり発言ではなく、事前に用意された発言であったということです。
鶴保氏の冷酷さのみならず、政策立案力の低さをも露呈した発言であったということです。被災地の実態を知れば、こんな発言はありえませんが、学ぶことよりもカネ集めが活動の中心だという、古い自民党的体質が露骨に現れた結果ではないかと思います。
学びにも色々あります。新聞やテレビやWEBや書籍からの学びもあれば、各地を回り、人々と触れあう中での学びなど、様々もあります。自分の目と耳を使って学ぶことです。
吉村大阪府知事の冷酷さ
維新の会党首の吉村氏は、大阪府知事兼大阪万博協会会長として、非常に冷酷極まりない対応を見せています。
「倒産して死ねということか」万博未払い、怒りの下請け社長が元請けの「ずさん管理」証言
2025/7/12 産経新聞
悲鳴をあげる下請け企業 海外パビリオン建設費を総額3億円以上未払い 元請け企業に要求
2025/7/10 産経新聞
大阪万博は、会場の夢洲の地盤が軟弱で工事が遅れ、パビリオンの建設も大幅に遅れ、開催そのものが危ぶまれる状況でした。しかし開催中止だけは何とか避けたい万博協会は、各国に参加を促すべく、パビリオン建設に関してもかなりの好条件を提示し、参加国確保を最優先に進め、何とか開催にこぎつけました。
開催後もパビリオンの建設が続くという、異例中の異例な状況下でも観客も徐々に増え、昨日は中間目標である観客動員数1000万人を突破したとのニュースもありました。万博はひとまず順調に所期の目的を達しつつあるかに見えますが、実はその陰で無残な出来事が進行しつつあります。それが、上記にご紹介した産経新聞記事にある建設費踏み倒し詐欺事件です。
万博開催から2か月以上も経っているというのに、パビリオンを建設した業者に建設費用が払われないという、国家的行事では100%ありえぬ踏み倒し詐欺事件がいくつも発生しているという。
しかも信じられないことには、万博開催を国に働きかけた維新の会会長であり、主催者である大阪万博協会会長である吉村大阪府知事は、踏み倒されて倒産の危機に瀕しているという業者に対して、万博協会は関知しない、税金で救済することはできないと責任を完全放棄した、無責任極まりない冷酷至極な対応で業者を突き放しています。
国と大阪府が主催する万博関連建設で支払いがなされず、踏み倒されるという詐欺被害に遭おうとは、いったい誰が想像できたでしょうか。北朝鮮以外では起こりえないような詐欺事件ですと書けば、北朝鮮からクレームが来るかもしれませんが、それほど異常です。
そもそも工期が遅れに遅れた中で、むりやりにでも開催日までに間に合わせるために、突貫工事をやらざるえをえない状況に追いやった全責任は大阪府と大阪万博協会にあります。時間的余裕のない中で、正規の契約書を交わさぬままに参加国の要求に応じて工費の嵩む作業を余儀なくされたケースも多々あったという。
日本国と大阪府が主催した万博に参加するのは、世界の国々やそれに準じる公的な機関です。しかも参加は武力で強制されたものではなく、各国の自由意思によるものです。
こうした世界的行事で費用は、主催国や参加国が要した費用を支払うのは当然すぎるほど当然のことです。これまで世界中で様々な万博が開催されてきましたが、会場建設に従事した業者への支払いが踏み倒されたという例は、この大阪万博以外では皆無です。
踏み倒した国がいくつもあるというのは、支払い能力の乏しい、あるいは万国共通の商道徳すら踏みにじる浅ましい国々までをも参加させた結果ではないか。おそらく万博協会は、口先だけ甘い条件をぶら下げて、余力のない国々をも強引に、むりやり誘ったのでしょう。大阪万博以外では起こりえない、異常すぎる事態です。
まずは大阪万博協会が未払い国と交渉して、未払金を業者に支払わせるべきです。この異常事の直接の責任は国にはありません。大阪万博協会が責任の全てを負うべきです。未払い国が払わないのであれば、チケット収入から大阪万博協会が業者に支払うべきです。これらの業者の犠牲的な協力なしには開催そのものも不可能だったことを思えば、協会としてはこういう事態になったことに対しては心からお詫びして、未払金の回収ないしは代替支払いを即刻実行すべきです。
世界的イベント開催に際して、こんな詐欺事までが発生するとは日本の恥。吉村会長を筆頭に大阪万博協会並び国は心から恥じるべきです。恥を知らない連中がますます日本をダメにしています。
ところで非常に不可解なことには、この異常な踏み倒し詐欺事件に関しては、産経新聞以外はどこも報じていません。わたしが日々接する西日本新聞もNHKも完全無視。RKB(TBS系)ラジオも、万博の宣伝になる万博訪問記を放送しても、この国家レベルの踏み倒し詐欺事件については全く報道していません。なぜなんだ!?
維新の会に関してもう一点。
維新の会の参院選の目玉政策は社会保険料を下げること、それも6万円も!社会保険料は労働者と企業側とで折半負担になっていますが、当然企業側の負担も下げることになるわけですが、削減額は合計で12万円という巨額に上ります。
社会保険事業の質を維持するなら、削減した分はどこかが負担せざるをえませんが、吉村代表は補填する財源については全く触れていません。言うだけタダという無責任な、政策以前の放言ではないかと思わざるをえません。
参政党と移民問題
自民党が脅威を感じるほどに、参政党の支持が急伸しているらしい。一方ではマスコミでの評判はかなり悪い。わたしも以下のブログでご紹介した体験から、
「二つの闇」と選挙「5.参政党からの投票依頼ハガキについて」
参政党は安心はできない政党だと思っていましたので、参政党が急伸して政局に影響を及ばすことになれば大問題だと思い、SNSでこの記事を再投稿し、注意を促すことにしました。
XとFacebookに以下のようなほぼ同文を投稿しました。
「「二つの闇」と選挙 https://ashi-jp.com/yami-two-senkyo/
参政党が急伸的に支持を伸ばしているらしいのですが、昨年10月の衆院選で体験した、参政党による異様な選挙活動について再投稿します。
「5.参政党からの投票依頼ハガキについて」https://ashi-jp.com/yami-two-senkyo/#index-5」
しかし、半日ほどでこれらの投稿を削除しました。というのは、参政党が急伸しているというのは、それなりの理由があるからだと思い至ったからです。それは、マスコミの集中批判を浴びている「日本ファースト=外国人・移民排斥」をメイン政策に掲げていることに関係しています。
まるで日本版トランプのようなスローガンですが、参政党が急伸しているということは、このスローガンに実感的に共鳴している人々が急増していることの結果に他なりません。とするならば、このスローガンに全面的に賛同しなくても、一理あると考えざるをえなかったからです。
本ブログの主テーマに沿った問題でも、歴代政権は、現在の日本も未来の日本をも支える基盤技術であるIT/AI技術者育成を自国内で行わず、日本の税金を投じて海外に育成を委ねるという国賊的な政策を延々と続けてきています。つまり、歴代政権は外国人労働者が激増するような政策を、長年にわたって意図的に実行してきたことになります。当然のことながら、この国賊的な政策は止めさせる必要があります。
参政党が急伸するのは問題ですが、多少の伸長は、政府への批判勢力としては、多少なりとも意義があるのではないかと思って、SNSは削除しました。参政党の急伸を受け、石破政権は選挙渦中であるにもかかわらず、在日外国人に関する対策を短期の間に具体化させ、関連部署の新設や法律の準備も進めさせるほどの異例の対応をとっています。
参政党の急伸はそれほどの効果があったわけですが、この効果を踏まえた上で、参政党の背後には、わたしの成りすまし工作に加担するような超異常な勢力がいるということも改めて強調しておきます
外国人労働者や移民については、単独で論ずべき大きな問題ですので、後日、あらためて取り上げることにします。
チームみらいという選択
最近、新しい政党が続々登場していますね。既成政党から有権者の気持ちが離れてしまっている時代を映し出したものだと思いますが、数ある新党の中で、これまで見たこともない、あらゆる意味で全く新しい政党が誕生しています。それがチームみらいです。
チームみらいの党首安野たかひろさんは東京都知事選にも出馬、5位の15万票余もの支持を得たそうです。チームみらいは、IT/AI技術者集団が作った政党です。日本の政治にもっとも欠けていた能力を、政党として丸ごと体現したような奇跡のような政党です。
スローガンも「政治問題をテクノロジーで解決!」ですが、単なるスローガンではなく、即形に移す能力をもった専門集団です。世界的に見ても稀な例ではないかと思いますが、停滞する日本を若さと技術で突き破ってくれそうな気配を感じます。
党首の安野たかひろさんは、日本のAI研究の大権威として有名な、東大工学部の松尾豊研究室出身のAIエンジニア。SF作家としても数々の賞を受賞している超異色の政治家です。
福岡選挙区の古川あおいさんも久留米附設から東大法学部→厚労省、情報学を学ぶためにアメリカのカルフォルニア大学大学院に留学、アメリカでIT/AI技術者として経験を重ねた後に帰国という異色の経歴の持ち主です。
余りにも高級すぎる経歴で、我々庶民とは無縁の世界の人々のような印象を持ちますが、安野さんの動画を拝見すると、ごくごくざっくばらんな親しみやすいお人柄ですよ。垣根がないという印象です。福岡選挙区の古川あおいさんも政見放送を聞くと、快活でお話がとても分かりやすい。
実は福岡選挙区にはもう一人、気になる候補がいます。公明党の下野六太さんです。正直いって、わたしはこれまで公明とは縁のない投票をしてきましたが、下野さんは、事実上、日本社会からは見捨てられたような扱いを受けてきた引きこもりの方々への支援策を、即実行段階の状態で公約として訴えておられます。
NHKの政見放送で聞いた下野さんのお話は、長らく中学校の先生をしておられたその体験からにじみ出るような、実のある方策が示されています。引きこもりについて公約として掲げているのは、下野さん以外にはないように思います。
福岡選挙区は一人しか選べませんが、チームみらいの古川あおいさん、公明党の下野六太さんお二人を同時に選ぶことはできませんが、迷うほどの候補者がいるということは、有権者にとっては喜ばしいことだと思います。皆さんも迷いながらも、一票を投じましょう。