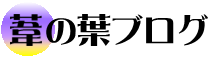次期学習指導要領改訂に向けて、中教審から「論点整理・素案」が提出されましたが、実践的なプログラミング教育に関してはほとんど変化はなし。ガックリきていますが、実践的なプログラミング教育がなぜ必要なのか。その理由について、0と1(ビット)で動く、デジタル技術の原形にまで遡って詳しく解説しています。また、デジタルには法治と透明性が必須不可欠であることも、その技術的特性に依拠して解説しています。(アイキャッチ画像はGeminiで作成。画像編集ソフトは前号同様Inkscape。)
目次
1.学習指導要領改訂素案
つい先日、次期学習指導要領改訂に向けて審議していた中教審から、論点整理(素案)が出されました。改定内容は、教育関係者が書かれたと思われる以下の記事に分かりやすく解説されています。学習指導要領は小中高を対象にしたもので、文字通り、日本の教育の中核的指針となるものです。
次期学習指導要領「論点整理素案」を読む:学校現場への影響と対応策
Yamamoto 2025年9月7日
改定素案の概略は新聞報道でも確認していましたが、上記記事でさらに詳しく、情報(IT/AI)分野の改定内容を知って、非常なショックを受けています。現状とほとんど変わっていないからです。その余りの変わらなさに、この原稿を書く気力さえ失せてしまったほどです。
翌日気を取り直して、改定素案に再度目を通したところ、改定内容では、以下のような目につく変化もありました。
「「主体的・対話的で深い学び」の実装」の一例として挙げられた、算数・数学分野の以下の事例です。
例えば算数・数学では、
- 従来の学び:比例、一次関数、二次関数を個別に暗記
- 深い学び:「関数を使えば未知の状況を予測できる」という中核的概念を理解し、日常生活の様々な場面で活用できる
算数・数学を単に計算としてしか教えないという、日本の数学の狭さについては、わたしもどこだったかで指摘しましたが、改定素案では、その狭さから開放されそうです。数学は単に計算能力を高める教科ではなく、改定後の子どもたちは、世界の認識を拡張するという数学本来の魅力を学ぶことができそうです。
ただしネットを見るとすでに、数学の一次関数、二次関数は、旧来型の暗記的な内容から、社会認識の強力なツールとしての学びに移行していますね。この変化はたった今知ったばかりなので詳しい事情は分かりませんが、学習指導要領は、むしろ後追い改定のような印象です。
では、最も気になる情報(IT/AI)分野ではどう変わるのかといえば、ほとんど変化はなし。
次期学習指導要領「論点整理素案」を読む:学校現場への影響と対応策
詳しくは上記記事をご覧いただきたいですが、以下の引用箇所には、IT/AI分野に対する改定素案の基本姿勢が明確に表れています。
「現場が陥りがちな誤解と正しい理解
誤解1:「情報教育=プログラミング教育」
正しい理解:素案では、情報活用能力を「①情報技術の活用」「②情報技術の適切な取扱い」「③情報技術の特性の理解」の3つの要素で整理しており、プログラミングは③の一部に過ぎません。むしろ、フィルターバブル(*注 インターネット上で自分の興味・関心に合った情報ばかりが表示される現象のこと)やエコーチェンバー(*注 同じような意見や価値観を持つ人たちだけで情報交換することで、特定の考え方が強化される現象)などの負の側面への対応を含む幅広い内容が重視されています。
改定素案では、情報教育はプログラミング教育にあらずと明確に定義づけされているように、情報教育の基本は情報機器をどのように使うのかという、使う側の立場からの指導が中心になっています。フィルターバブルやエコチェンバーなどの危険性を教えることも大事だとは思うものの、そういう現象を生み出す仕組みについて教える内容は皆無。
フィルターバブルとエコチェンバーは表裏一体の関係にあるわけですが、ネット空間特有の視野狭窄症に陥らせる超偏向誘導は、アルゴリズムによって意図的に生み出された人工的な罠であることを、原理的に理解させることこそが重要ではないかと思います。
子どもたちは、仕組みも何も分からぬまま、ただ危険だよと言われても、モヤモヤとした靄のような感覚でしか受け取れないはず。
ネット空間を飛び交う膨大な情報は、自然発生的に生まれて浮遊しているのではなく、全て明確な意図をもって作成されたものであり、視聴者が目や耳で確認できる画面上に表示される文章や画像や音だけで全てが完結しているのではない。画面の裏側には様々な仕掛けがなされているという、デジタル技術で構成される、ネット空間特有の仕組みを原理的に教えるならば、子どもたちの眼前を覆うモヤモヤも晴れ、覚醒した状態でネット空間の危険性についても冷静に理解することができるはずです。
2.実践的なプログラミング教育の必要性
とはいえ、小学生にはアルゴリズムなど理解できるはずはありません。アルゴリズムそのものを教えるのではなく、アルゴリズムを生み出す基盤となる技術の特性を、具体的かつ実践的に学ぶ機会を提供すれば、小学生でも十分に理解は可能。むしろ楽しみながら学んでくれるのではないかとさえ思います。
デジタル技術については、座学で暗記科目的に学ぶのではなく、手を使って実践的に学ぶべきだというのはこれまでも繰り返し指摘してきましたが、小学生のみならず、中高生も同様です。デジタル技術は知識を暗記するだけでは、その本質を理解することはできません。実際に手を使って具体的にデジタル製品(ホームページやゲームやアプリなど)を作成する中でしか真の理解を得ることはできません。これは大人でも子どもでも同じです。
HP作成からデジタルの本質を感得する
その実践的なプログラミング教育の具体的方法については何度も提案してきましたが、ホームページ(HP)を実際に作成させることが、単純かつストレートにデジタル技術の本質を理解させる最も有効な方法だと思います。システム構築などに必要な本格的なプログラミングでは、デジタル技術の全貌を掴みその本質を理解する前に、目前のプログラミング言語や文法(決まり事)との格闘に精一杯で、デジタルの本質を理解するまでには至らないと思います。教材の工夫次第にもよりますが、全ての児童生徒が学ぶにはかなりのハードルがあります。
しかしHPは、本格的なプログラミングによる作成物よりもはるかに単純な仕組みで構成されていますので、子どもでも理解は可能です。少なくとも中学生は例外なくほぼ全員が理解できるはずです。
本格的なプログラミングは、直接コンピュータに指令を出すプログラミングを書き連ねることで構築物を完成させていきますが、HPはマークアップ言語と呼ばれるHTMLと、装飾やデザインの補助的機能をもつCSSというプログラミンの言語体系を基盤にしています。HPの画面を構成する様々な要素(文章や画像や音楽など)を定義づけする、タグと呼ばれる記号や文字を使って構成していきますので、構造としては単純、複雑ではありません。マークアップ(印づけ=定義づけ)言語と呼ばれるゆえんです。
ごく簡単なHPなら数行で完成しますので、小学生でも作成可能かとも思いますが、小学生の場合は、HPそのものを自分で見るということはほとんどないと思いますので、HPそのものに慣れ親しんでいないという点で、小学生にはHP作成は親和性に乏しいかとも思います。
小学生には別の提案をしたいと思いますが、HP作成の効用についてもう少し書くことにいたします。
HP作成がなぜデジタル技術の本質を理解する最短の道なのかといえば、単純なものであれ複雑なものであれ、完成したHPを見れば、即座にデジタル技術固有の特性や本質が瞬時に感覚的に理解できるからです。
文章や画像や音楽などはその属性を示すタグをつけて記述していくのですが、文字で構成される文章がそのまま画面に表示されるのはある意味当然なので驚きませんが、画像や音楽なども全て文字や記号で表示されています。にもかかわらず、表の画面上には絵や写真が表示され、音楽が演奏されます。大人でも子どもでも、最初にこの瞬間を目にして驚かない人はいないと思います。
この驚きとは、デジタル技術は全てのモノを文字と記号に変換して、実物と同価値のモノとして存在せしめる技術であることを体感的に受容したことにほかなりません。つまり、デジタル技術とは、文字や記号で構成されるものだというデジタルの本質を、驚きの瞬間に理解したということです。これらの文字や記号は元をたどれば0と1の数字(ビット)ですが、この点については後に詳述します。
わたしは繰り返し、デジタル技術の理解習得には驚きが重要なカギを握ることを指摘してきましたが、デジタルを目にして感じた驚きとは、世界認識の大転換をもたらすことになるからです。この世界認識の大転換は、子どもであれ大人であれ、デジタル技術の本質を理解したことを意味しますので、以降のプラグラミングなどの学びを底支えする大きな力になるはずです。
対象に作用してAからBに変容させたり、AからBへ移動させたりと、対象に対して何らかの変化や動きを加える際には、デジタル以前には物理的な作用を加えたり、化学的な作用を加えることで、必要な変化を生み出してきました。
例えば、従来の映画では、実際に映した映像や実際に録音した音や音楽などを映写機や録音機などでそのまま投写、再生するという物理的な操作によるものですが、現在のデジタル化された映画は、文字や記号で表記された画像や音楽が実体のある映像や音楽としてスクリーンに投写されます。記号や文字に変換された画像や音楽は、実物をそのまま録画録音したものとは違い、夾雑物が入り込む余地はないので、再生装置の機能にもよるとはいえ、非常にクリアに再生されます。それを味気ないと感じる人もいるようですが、これもデジタルの特性のひとつです。
Scratchで学ぶプログラミング
ここで、二つ目の学びの方法をご紹介します。小学生を対象にしたものですが、Scratchというアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)のメディアラボで開発された、子ども向けのプログラミングソフトですが、世界中の教育現場で使われているという。
Scratch(スクラッチ)でできること|プログラミングで遊びながら身につく力とは?
LITALICOワンダー
オンラインが標準のようですが、オフラインでも使えるアプリ版もあるという。ゲーム感覚で楽しみながらプログラミングの基礎が身につく優れもののようですが、プログラミング言語が分かりやすい日本語表記になっており、日本語表記の指示どおりに動かせば、プログラミング作品が完成します。
プログラミング学習用に作られたソフトですので、本格的なプログラミングの基礎が楽しみながら身につく構成になっていますので、子どものみならず、IT/AI無縁であった中高齢者の学び直しのスタートにも使えそうです。
このScratchは、言葉による指示によって画面上のキャラクターたちを動かしたり、音を出したり、様々な変化を加えたりできますので、プログラミングとは、言葉の指示によって対象に作用する技術であることは、自ずと実感的に理解できる仕組みになっています。
Scratchからスタートすると、デジタル技術の基本的な本質を理解することができるだけではなく、本格的なプログラミンの学習にもシームレスに移行できますので、学び方としても効率的だともいえそうです。
しかしデジタル技術とは、文字や記号という言葉によって世界に作用し、世界を動かす技術であることを視覚的に瞬時に伝える強度においては、HPの場合と比べると弱いという印象です。義務教育でのプログラミング教育(情報学教育)の目的は、プログラマーの育成ではなく、デジタル、ビットの世界の本質を理解させることに置くべきですので、その理解をより促進する学習方法を選択すべきだと思います。
現在の中学校のプログラミング教育でもScratchが使われているようですが、何とプログラミングを使って五角形を作成させています。こんな作業で何を学び、何を発見するのでしょうか。そもそも五角形を作図しても楽しくも何ともないはず。
それどころか、以下の記事によれば、複雑な数学的思考や計算が求められる難解さ。プログラミングに興味をもつきっかけにすらならないはず。それどころか、ビットの世界の片りんも理解できない、難解至極なだけの課題であったという。これも、プログラミングには、高度な数学が必要だと力説する新井紀子氏の影響でしょうか。
2021年4月28日
中学の技術の授業でプログラミング! ただ、課題はかなりムチャ振りでした・・・
HPなら、中学生にとっては楽しみながら作成できるはずです。文字と画像だけの簡単なHPから始まり、様々な装飾を加えながら、音楽を入れたり、画面上に動きのあるアニメーションを登場させたりと、段階を経ながら、卒業するまでに、公開して閲覧してもらえるようなHPを完成させることを課題にすることを提案いたします。大人の学び直しにもHP作成は必須です。
これらの段階を経るならば、HTMLというHP作成に必要なマークアップ言語と、装飾やデザインを担うのCSSを学び習得することになります。そして動きを加えることで、プログラミング言語としては応用範囲の広いJanvaScriptも学び習得することが可能になります。合わせて、文章や画像や音楽や動画やアニメを定義づけるファイルの違い(拡張子と呼ばれるもので、txtやjpgなど多数あり)についても、同時に必然的に学ぶことになります。
JavaScriptとは?できること・作れるもの、難易度、基本文法などを初心者向けに解説
2025/08/22 IDH
Node.jsとはなにか?なぜみんな使っているのか?
2023年05月23日 Qiita
こうした実践的なデジタル応用技術の実態を知らないままでは、ファイルはファイルという普通名詞で認識するだけですので、細部にわたって定義づけ(属性を明確化)することがデジタル(ビット)の特性であることも理解できぬまま、ただデジタル機器を使うだけの人になってしまいます。
HP作成は、本格的なプログラミングより格下に見られがちですが、生成AIを含む、WEB空間を構成する基本を学ぶ格好の素材だと思います。
そして、このHP作成を学習しながら、生成AIを学ぶことも必須にすべきです。簡単なHPから複雑なHPへと段階を経ながら学びを進める中で、各段階ごとに、同じテーマ、構成で生成AIにHP作成させ、そのAI作のHPと自分がコーディングしながら作成したHPとを比べてみる。
コードを比べると違いがより明確になるはずですが、その違いはプロンプトの内容の何に起因すのかも考えると、プロンプト作成のポイントを掴む勉強にもなるはずです。
もちろん、こういう実践的なプログラミング教育は専門業者に依頼すべきだと思いますが、改定素案では、業者への依頼は全く想定していないようです。全てを教師の担当になるらしい。この体制がそもそも大問題です。
デジタル音痴が日本の輸出を阻害
歴代政権が輸出産業として支援に力を入れてきたコンテンツ産業は、石破総理も、アニメなどの輸出額は自動車輸出に匹敵する5兆円規模にまで上るとして、さらに支援を強化する方針を発表していました。しかしアニメや漫画などの輸出額5兆円のうち、日本のコンテンツ企業が手にするのはその半分以下です。デジタル作品は、デジタル作品の流通を担う企業ががっぽり儲けているからです。
しかもデジタル時代では、デジタル的な流通を可能にするような作成方法を採用しなければ不利になるのは言うまでもありません。
日本の漫画は世界的に人気がありますが、その流通形態は旧態依然。韓国の漫画は、スマホでも楽々閲覧可能なスクロール方式を採用して話題になりましたが、日本の漫画は紙製本そのままの、複雑なというべきか、変化に富んだレイアウト、面割りがなされていますので、漫画をそのまま画像化してデジタル漫画として出版しても、そのままでは、スマホでは読むことは難しい。日本の漫画はここが大きなネックになっているはずです。先日、このネックの存在を指摘する出版社の声を耳にしました。
実は、皆さんも無意識のうちに体験済みだと思いますが、HPでは、PC対応の横に広がるレイアウトでも、スマホなど小さな端末見ると、見やすいように立て並びにレイアウトが変わります。
これは、端末に合わせて自動的にレイアウト表示が変わるような、コード(プログラミング)を書き加えているからですが、このレイアウト自動変更プラグラミングは、HP作成では標準仕様となっています。PCでは横広がりのレイアウトが、スマホでは自動的に立て並びに変わります。
HPの基本的仕組みを一度でも学んでいれば、漫画のレイアウトをHPと同じように、端末の大小に合わせてレイアウトを変える手法の適用をすぐにも思いつくはずです。もちろん、HTMLを基本にしたHPと画像構成の漫画とでは、その変換には難易の差はあるとはいえ、変換へのきっかけはなるはずです。
優れた漫画作品を作成しても、それを世界に向けてスムーズに流通させる手法を自ら案出できない日本の出版社は、まさにデジタル音痴ゆえに、輸出で得ることができたはずの収益をみすみす手放しているわけです。現代は、デジタルとは無縁で存続できる領域はないと、日本中が認識すべきです。
このデジタル音痴解消には、実践的なプログラミング教育あるのみです。
中学卒業までには、Scratch(小学校)とHP作成+関連する生成AI、高校卒業までには、中学生までの学習に加えて、プログラミングと生成AIをセットにした実践的な学習をし、高卒段階で、基本的なプログラミングを習得して、生成AIが作成したプログラミングの正否の確認をする程度の力を習得することを基本目標にすべきです。
3.世界を記号化するデジタル・ビットの世界
デジタル世界では、文字や記号を使って、対象に対して様々な変化を生み出しています。しかもこの対象は、人間が認知しうる森羅万象、あらゆる世界を対象にしうる可能性を秘めています。なぜそれが可能なのかといえば、デジタルとは、人間の対象となるあらゆる世界を、文字や記号に変換しうるとする志向性に依拠して存在する技術だからです。
「志向性」としたのは、世界にはまだ文字や記号に変換されていない対象が無数に存在しているからですが、それらもやがて文字化され、記号化されることになるはずです。
それらの文字や記号は、元をたどれば0と1の数字(ビットと呼ばれています)の組み合わせにすぎませんが、無数にある0と1の組み合わせに意味を持たせ、人間が認知しうる文字や記号に変換したものがプログラミングで使われる様々な言語です。
プログラミングの原形は、無機的な0と1の数字の組み合わせにすぎないのであれば、後付けでそれらの数字に人間語である文字や記号を当てはめても意味があるのかとの疑問が湧くかもしれませんが、0と1の数字の組み合わせは、組み合わせ方によってそれぞれに違いが生まれます。
ビットとは?概要をわかりやすく解説
2024.09.29 IT用語一覧
それら組み合わせの違い、差異が意味の違いの基となるわけですが、その違いは、コンピュータにとっても一種の言語(信号)として認識しうるもので、人間が使う自然言語に対してコンピュータ言語や機械語と呼ばれたりします。しかし当然のことながら、コンピュータは、人間の使う自然言語は理解できませんので、自然言語を機械語に翻訳(コンパイル)してコンピュータに指示を届けます。
こうした処理をコンピュータ内で行うのが半導体です。
コンピュータの仕組み そしてなぜ 半導体がなぜ必要か
2021.12.02 ramble
コンピュータには0と1を使った機械語に翻訳されて伝えられるとはいえ、人間が言葉で出した指示がコンピュータに伝わり、人間の指示通りにコンピュータが処理するという仕組みは明確です。
つまり、デジタル技術が切り開いた世界とは、人間が指示を出してコンピュータを動かすことを可能にしたということです。人間の指示とは、人間の言葉によってコンピュータを動かすということです。そして今や、ありとあらゆるものにコンピュータが搭載されていますので、世界は人間の言葉で操作されるモノに囲まれていると言っても過言ではありません。
こんな世界を意識し始めると夜も眠れなくなりそうですが、我々は、事実としてこの現実を認識する必要があります。この現実を認識する機会を提供することこそが、プログラミング教育のもっとも重要で基本的な目的とすべきです。
生成AIの進化で大量のプログラマーは不要な時代へと移行しつつありますが、そもそもわたしが提唱しているプログラミング教育は、プログラマーの育成を目的にしたものではありません。プログラミング教育を通して、人類史を画する、デジタル技術が生み出す世界の実相を理解させることにあります。
生成AIの登場以降、人間に代わってAIが何でもやってくれそうな動きが加速度的に進んでいますが、この生成AIはむしろ、我々人間の目からデジタル技術の存在を遮蔽しているだけではなく、隠蔽する役目さえしています。プロンプトという人間が使う自然言語で指示を出せば、瞬時にその結果を返してくれるので、その応答を可能にしているデジタル技術の存在やその技術の特異性などは想像する余地もないからです。
生成AIの使い方を学んでも、生成AIを生み出した技術については全く無知のままです。生成AIを仕事で使わざるをえない場合は、取りあえずその使い方をマスターする必要はあるとはいえ、学校教育では、生成AIの使い方を教える前に、生成AIを含む新技術を生み出してきた、デジタル技術、ビットの本質をこそまず学ばせる必要があります。
その本質とは、繰り返し指摘してきましたように、デジタル技術とは、文字や記号などの言葉による指示によって構成され、構築される、人類史上初の技術だということです。これらの文字や記号の原形は0と1のビットと呼ばれるものの組み合わせで構成されていますので、アメリカではデジタル登場後の現代を、ビットの世界と呼ぶ学者もいるほどです。全てのものが0と1に分解される時代という意味だろうと思います。
全てのものが0と1に分解されるといえば、連想されるのが遺伝情報を記録したDNAですが、人間のDNAと動物や植物など他の生命体とのDNAとが、ごく一部に違いがあるとはいえ、基本的には全ての生命体がほぼは同じであるという点でも、DNAとビットとは似ていますね。
DNAのこの事実を発見した科学者は、大驚愕しただろうなあと思いますが、DNAのこの驚愕すべき発見は、人間の祖先は、動物や植物などの他の生命体と同じであることを物語っていますね。実感としてはなかなか理解しがたいですが、日本を含めた世界中の科学者たちは、その生命の起源を求めて宇宙にまで探索の射程を拡げています。
ところでDNAとビットとは似ているとはいえ、DNAは自然の中から生まれた生命の記録簿のようなものですが、デジタルは100%人間が人工的に作りだした、世界を記号化する装置です。その記号化への志向性がついに人間の脳にまで及んでいるというのが、AIであり、生成AIであると単純化することも可能です。
これがビットの現在地ですが、事態はさらに進みつつあります。人間が人為的に作りだした人工的な技術を使って、生きた人間の脳とコンピュータとを繋ぎ、一体化する試みがかなりの確度をもって進められています。やがて、コンピュータと人間の生体とが文字通り一体化する世界が出現する可能性も否定はできません。人間が人為的に作り出した人工物が、人間の生体という自然物と一体化ないしは溶け込むということ。その可能性がセロではないということです。
そういう時代を生きていかざるをえない我々にとっては、あり得ぬことをあり得ることにした技術の正体ないしはその本質を知ることは、無知からくる不安を払拭するだけではなく、人知を超えた技術を暮らしを支える力に変換する出発点にもなるはずです。
4.ビットと独裁 *9/14追記 *9/15追記
デジタル、ビットの本質を理解したならば、何をされるかは分からないとの不信を抱かざるをえない相手(国や企業)からは、うかつにデジタル製品は買えない、買いたくないという判断に傾かざるをえません。
中国製のEV車が、低価格、高品質を武器に欧州車を蹴散らして売り上げを伸ばしているようですが、特に車などは簡単に遠隔操作が可能ですので、デジタル製品の中ではもっとも危険といえば危険な商品でもあるわけです。
中国企業は、共産党政府の管理監督下にあり、政府の命令に背くことは不可能ですので、ある特定の人物をマークせよとの命令を受けた場合、それを拒否することはできません。目に見える危害を加えられないかぎり、マークされ情報を収集されていることにも気づかないと思われますが、十分ありうる想定です。
これは中国製スマホやPCなどでも起こりえますね。
以下の記事は、いわれなきスパイ罪で7年もの間、中国の刑務所に「幽閉」され、先日解放されたばかりの日本人男性、鈴木英司が身をもって体験した中国の恐ろしさを、勇気をもって公表したものです。
危険な習近平体制と弱腰の日本大使館…北京で突然逮捕、7年間「幽閉」された日本人からの警告「今、日本人が中国に行くことは絶対に勧めない」
木俣 正剛(元「週刊文春」・月刊「文藝春秋」編集長)
2025/10/14 現代ビジネス
鈴木氏は、長年日中友好に尽くしてこられた、バリバリの親中派だったという。そんな人物に対してすら、いわれなきスパイ罪で刑務所に放り込み、痛めつけるのが習近平氏を頂点にした共産党中国です。
ただ鈴木氏が、言論の自由が保障されている日本に帰国した後も、この事実を公表するにも勇気を要したというのは、日本政府(外務省)が中国への忖度を優先して、恐怖の中国体験を口外しないようにと口止めし、日本国民を本気で保護する意思がないからだという。他にも類似例は多数あるにもかかわらず、日本政府から口外しないように口止めされていますので、鈴木氏以外は誰も中国での恐怖体験は公にはしていないという。
日本政府・外務省が、これほど卑屈にも中国に膝を屈する対応をしてきたとは信じられませんが、事実なんですね。何のために日本政府は存在するのか。この事実を広く報道しないマスコミにも重大な責任がありますが、自民党総裁選では、本気で日本国民を守る覚悟をもった総裁の誕生を望みます。候補者の中にいるのかどうかは分かりませんが、石破総理を辞任に追い込んだ動きにも、同様の思いによるものがあったはず。
総裁選の前倒し要求は、まず国会議員から出てきましたが、やがて自民党の都道府県連からも続々と前倒し要求(事実上の石破降ろし要求)が出るに至っています。石破氏にはその実績からも地方の党員に支持者が多いと言われてきましたが、今回の前倒し要求では、国会議員よりも地方の方が先行していましたね。
石破氏が辞任を決意するに至ったのは、菅、小泉氏の説得を受けたこともあったとはいえ、地方党員からの前倒し要求が想定以上に多かったことも辞任決断の大きな理由だったと思われますが、マスコミでは、地方からの要求の多さに着目した論評がないのは非常に不可解です。
地方から石破降ろしの声が上がったのは、いうまでもなく、後に誤解だと打ち消しに走ったとはいえ、石破総理が、アフリカとのホームタウン推進策に象徴されるような、日本よりもアフリカ、海外が大事だというパフォーマンス外交がトリガーになったのは間違いないはずです。
総裁選では、というよりも、政治家の皆さんは、日本人のIT/AI人材を放棄したまま、海外でのIT/AI人材育成を優先するような政策は即刻改めていただきたい。
自国で、実践的なIT/AI人材を育成を放棄した日本は、中国に引き離される一方です。
中国・月泉仿生が高性能ロボットハンド、糸通しも円滑 介護参入狙う
2025年9月11日
キャップ開けから糸通しまで⋯世界最高「38自由度」のロボットハンド、中国で誕生
2025年9月11日 36Kr(*上と同じ内容記事ですが、上は有料で一部しか読めません。)
北京理工大学は、生きた昆虫の脳を制御する「サイボーグバチ」の開発に成功しています。
生きた昆虫を脳制御。超薄型電子回路装着「サイボーグバチ」、国防任務に実用化
Forbes JAPAN 2025.09.11
生命体の脳とコンピュータとを一体化させる試みの一つです。表向きは民生用に活用するとしていますが、極小の恐怖の生物兵器にも転用可能。おそらく、「サイボーグバチ」を生物兵器に転用することも隠された目的の一つだと思われます。それにしても、超高度な技術(*ハチの脳の制御を可能にする極薄のチップの開発と、このチップを使ってハチを遠隔操作するデジタル技術の援用)を開発する中国人の頭脳には驚くばかり。やがて中国人によって、人間の脳を制御する技術も開発されるのではないか。との恐怖が膨らみます。
中国人のエリート層の頭脳は世界最先端に位置するとはいえ、何をされるか分からないという不信の塊でしかない中国政府と、そのコピー的存在にならざるをえない中国人によって作られたデジタル機器は、どれほど優秀であっても使う気にはなれません。
とは思うものの、以下の中国企業シリウスジャパンの超格安ロボットには、人手不足が深刻な日本企業も飛びつく可能性は高い。
月額5万円の衝撃「ロボット民主化」時代の幕開け
2025年9月9日 (火) LOGISTICS TODAY
ロボットにはデジタル技術満載ですが、上記のロボットは単純作業ですので悪意ある工作を施す動機が生まれる余地はなさそうですので、デジタルゆえの危険性は低そうです。
しかし、デジタル機器、デジタル製品の特性に基づく危険性を繰り返し指摘しているのは、デジタル技術の共有(デジタル製品の使用や購入)は、信頼がなければ成り立たないことを訴えたいからです。
ビットの世界は、法治(明確なルール)と透明性なしには共有は不可能だということを中国をはじめ、独裁下にある国々の統治者は認識すべきです。デジタル技術の応用では、中国人の優秀さは驚きをもって認めざるをえませんが、その優秀な頭脳で生み出されたデジタル製品は、「不信」の箱に収納されて輸出されても、誰も使おうとは思わないということです。
*9/14 追記 強力な習近平独裁体制下にある中国ですが、かすかながら希望がないわけではありません。以下の記事にあるように、海外在住の中国の優秀なIT技術者が、その高度なIT/AI技術を駆使して、中国共産党による独裁体制批判を公然と展開する動きが出始めているからです。
「奴隷にされたくない」中国で打倒・習近平の蜂起呼びかけ、英国から遠隔操作…ハイテク振興の裏で進化する反共運動 JBPress 2025.9.12
技術者による最新技術を使った反体制運動である点が、従来の政治的な運動との違いを際立たせていますが、ビットに基盤を置いた最新技術は、独裁とは相いれないという本質論からしても、習近平的独裁体制の永続は困難ではないかと思われます。*9/14 追記
*9/15 追記 そういえば、中国系の動画共有アプリのtiktok問題もありましたね。tiktokのアメリカ事業をアメリカ企業に売却せよという米国政府の要求ですが、これはバイデン政権時から続く問題です。トランプ大統領は、若者の利用者が多いtiktokからの応援で支持率を伸ばしたとも言われており、ご自身もアカウントを開設して利用していますが、tiktokの売却要求は前政権から引き継いでいるようです。
米中貿易協議始まる 関税措置に加え「TikTok」についても議論
2025年9月15日 NHK
爆発的に利用者が増えた中での売却交渉は難しいと思われますが、tiktokの利用者の情報が中国政府に渡る可能性についての米国政府の懸念は、当然すぎるほど当然です。しかし言論や表現の自由に関わる問題でもありますので、米国政府としても強引な手段は執りづらいというジレンマがあるでしょうね。
何をされるか分からいと、相手が信頼できない場合、デジタル製品を利用することには抵抗を感じる、あるいは利用したくないという反応が不可避となっている現代の時代相を、習近平中国はとくと認識すべきだろうと思います。*9/15 追記
Illustratorがしつこく貼りついてくる
本号のアイキャッチ画像は、冒頭の注にありますように、画像はGoogleのGeminiで作成し、文字入れのごく簡単な作業はInscapeを使ったのですが、画像をブログに挿入する前に画像を確認しようとしたところ、前号Adobeのアカウントが乗っ取られたの後半に追記的に書いたIllustratorの勝手な起動が発生。
すぐさまIllustratorを消したのですが、念のため画像のプロパティを開くと、Illustratorのロゴが二つも表示されているではありませんか。画像を開くアプリはデフォルトでMSのフォトに設定していたのですが、前回と今回はIllustratorが開きました。この2回以外には皆無。
余りにもしつこいのでIllustratorのアプリをアンインストールしようとしたのですが、削除できません。削除するにはアカウントで所有権を確認する必要があるとの表示。メールアドレスを入力すると、アカウントを復活しますかの質問。
Illustratorが勝手に起動して編集ページが開き、使用可能な状態にあるにもかかわらず、アプリを削除しようとするとアカウントでの確認が必要だとの表示。もう無茶苦茶。Illustratorをお使いになっている方は、これはありえない現象であることはすぐにもお分かりいただけるかと思います。
いかにもIllustratorでアイキャッチ画像を作成したかのような異様な工作は、アイキャッチ画像の真の作者はわたし久本福子ではなく、別にいるという捏造工作の一環であることはいうまでもありません。そしてその捏造工作は、わたしの成りすまし工作にもつながっています。
アイキャッチ画像のプロパティにIllustratorのロゴが入ってしまっていましたので、画像を作り変えました。たとえ、ビュアー段階とはいえIllustratorのロゴが表示されていることには我慢がならなかったからです。
同じ現象があった前号のAdobeのアカウントが乗っ取られたのアイキャッチ画像にはAdobeのアカウントが乗っ取られたのマークは残っていませんでした。
こんな異様な工作をいつまでもしつこく、Adobeが組織的に加担するとは考えられませんが、わたしのPC操作だけで、アプリのアンインストール阻止や、Adobeアカウントの確認要求など、手の込んだ工作ができるのかどうか。
誰に言えばいいのか。わたしに張り付くのは、もういい加減に止めろ!
Xでまたもやアイキャッチ画像の自動挿入妨害
今日(9/14)、XとFacebookに更新お知らせの投稿をしたのですが、Xでは、またもやアイキャッチ画像の自動挿入が妨害されました。アイキャッチ画像が自動挿入されない場合は、画像が大きく表示されてもその画像からはサイトに遷移できず、サイトへの誘導率が下がります。
日本人の貧困を加速する石破総理の最後に追記しましたように、アイキャッチ画像をめぐる異変は、イーロンマスク氏がトランプ政権の閣僚を辞めた5月末以降、数か月にわたって続いていたのですが、この異変をネットに公開するや即座に異変は消え、正常にアイキャッチ画像が自動挿入され、やれやれと思っていました。
ところが本日、当ブログの更新のお知らせを投稿しようとしたところ、またもや画像の自動挿入が妨害されました。やむなく、画像を手動挿入して「またもや妨害復活」と書き添えて投稿しました。Facebookでも更新お知らせを投稿しましたので、その投稿の最後にXの異変も記しました。
この後、Xを確認したところ、アイキャッチ画像の自動挿入OK!正常に戻っていました。そこで、字数制限なし、何時でも編集OKのFacebookに以下のように追記しました。
|
Xでは、アイキャッチ画像は自動で挿入されず、またもや画像は手動挿入に逆戻り。Xでは、画像からサイトには遷移しません。このブログの何がXに忌避されたのかは、不明。
*****
と投稿した後、Xを試したところ、画像が自動挿入され、アイキャッチ画像からもサイトに飛ぶことができました。
ということは、この異変はXの内部からではなく、わたしのPCに侵入しての操作だったのか。わたしのPCから、アイキャッチ画像の自動挿入を妨害することが可能なのでしょうか。
|
なお、画像を手動挿入したXは削除しました。