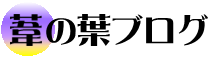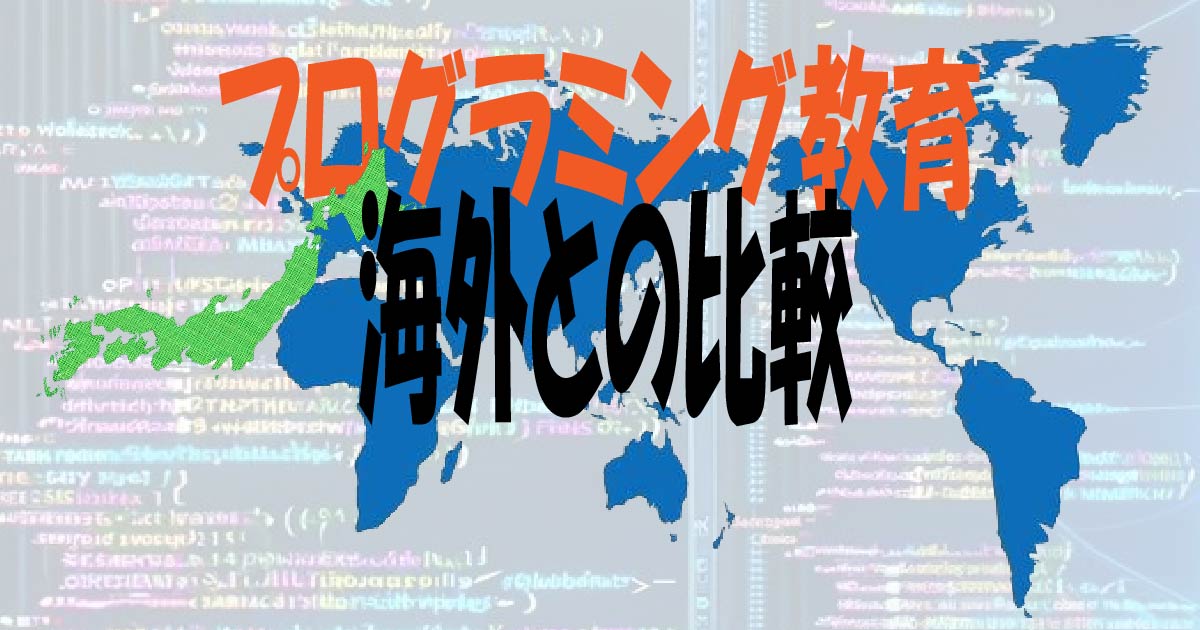日本のプログラミング教育の特異性は、海外のプログラミング教育と比較するとより鮮明になってきますが、その違いを一言でいうと、日本では、プログラミングの実技と理論の学習を完全に分離して実施しているのに対して、海外は両者を一体化して教えているということです。結果は明白ですね。また副産物として、海外の事例から道州制の危険性が事実として証明されました。最後に、石破総理の関税対応批判も。(アイキャッチ画像のプログラミング画像はBingイメージクリエーターで作成、世界地図はフリー素材を使用、日本地図はAdobeExpressで作成。)
目次
1.「論理的思考力」の空論性
これまでも、新井紀子氏が日本のデジタル教育を阻害したことを繰り返し批判してきましたが、本号では、教育面におけるその弊害について具体的に検証することにいたします。
日本でも遅ればせながら、2020年から小中学校でのプログラミング教育の実施が始まっていますが、すでに指摘しておりますように、全く実用の用に役立つような教育は行なわれていません。その最大の原因は、日本ではプログラミング教育の狙いは、以下の記事にあるように、<難しいプログラミング言語を覚えたり書いたりすることではなく、「論理的思考力を身につけること」にある>からです。
小・中・高のプログラミング授業が必修化!それぞれいつから始まる?
スタープログラミング
しかもこの「論理的思考力」の育成という教育方針は、目下の日本の教育行政における基本的な指針になっているといっても過言ではありません。国語教育においても論理的思考を養うとして、お知らせのような文例が使われたり、新聞が教材として推奨されたりもしています。
つまり、日本の文部行政が指針とする論理的思考とは、非常に単純かつ皮相な理解に基づいて策定されており、むしろ国民の論理的思考力や国語力、言語力を低下させる逆効果を発揮しているとさえいえます。言語能力の低下とは、すなわち思考力の低下そのものを意味しており、非常に皮肉な結果をもたらすに至っています。
論理的思考とは、例えば新聞記事に代表されるような三段論法的な起承転結が明確な文章などによってのみ育成されるものではなく、むしろ情動的、感性的な感能力をも含む、総合的な言語活動、言語体験によってこそ強靭な思考力は育まれるものだと思います。
ちなみに、フィンランドも新聞を教材に使っているそうですが、なんと、新聞記事が事実かどうかを子どもたちに調べさせる授業をしているそうです。情報が事実かどうかを検証する能力は、情報が氾濫する現代においては必須不可欠の能力ですが、物事を批判的に検証するという訓練は、人間の思考力を高め、強化するための最上の効果を発揮します。全てを無批判に受け入れることは、思考力を鈍麻させるだけ。
こうした人間の思考力の源泉を無視した、日本の文部行政によって推進されている皮相な思考力育成指針は、プログラミング教育を推進するための基盤づくりを目指したものであったはずですが、肝心のプログラミング習得にも全く役立ってはいません。その最大の原因は、論理的思考力の涵養が、プログラミング実技とは完全に隔離されてなされているからです。
これは、論理的思考力の源泉を全く無視した皮相な指針から導き出された結果に他なりませんが、プログラミング教育の空論的定義に基づいたものです。
その空論的定義を象徴的に表現したのが、前号でもご紹介した以下の動画で披露されている新井紀子氏のお考えではないかと思います。
プログラミングと不可分であるアルゴリズムには数学的な知識は不可欠だとはいえ、数学の知識の乏しいプログラマーは使い捨てにされるだけだとして、数学を学ばずにプログラミングだけを教えるのは無意味だというのが新井氏の結論の一つだと思いますが、数学の知識の乏しい素人のわたしからすると、全く逆だと、自信をもって反論したい。
2.空論的プログラミング教育
以下、この反論を展開していきますが、数学的知識はプログラミングのみならず、人が生きていく上でも必須の学問分野であり、世界認識を拡張する学問であると同時に論理的思考力育成の基礎的領分を占めているのは、世界共通の認識だと思います。
しかし、新井氏が主張するプログラミングには数学が必須であるという際の数学とは、世界の共通認識としての数学一般ではなく、おそらくアルゴリズムの基盤となる高度な数学につながる領域の数学をを想定しておられるはずです。
実は昨今の小学生の教材には、この高名なAI学者であり数学者である新井氏の示す指針に沿った、数学の萌芽的な学習方針が反映されたような変化が見られます。わたしが実体験的に確認したのは小学校だけですが、おそらく、中高の教材にも同様の変化が見られるはずです。
とはいえ、わたしは特にこの方面の調査をしているわけではなく、学童で子どもたちが宿題をする際に偶々目にした程度で、非常に限られて見聞にしかすぎませんが、その限られた見聞の中でも、以前には目にしたこともない、新領域の内容が算数に導入されていることに気づいて以来、何が狙いなのかと、ずっと気になる変化でした。
様々なものを分類させる問題と、それをベースにした派生的問題群です。こんな問題はわたしの子ども時代にはもちろん、うちの子どもたちの時代にもありませんでした。学童でも以前には見かけたことはなく、比較的新しい領域ですが、当初はこの新領域導入の狙いは全く想像もできませんでしたが、生成AI登場後、素人ながらAIの仕組みについても多少は学んだ結果、これはどうやらAIのラベリング(AIの精度を左右するデータラベリングとは?必要性や方法を解説)や、プログラミング習得に必要な知識の基礎を習得させることが狙いらいしいということに思い至りました。
おそらくこの変化は、小学校で始まったプログラミング教育の実例の一つだろうと思います。理科や社会でもグラフやデータの読み取りなどを問う問題も増えていますが、おそらくこれらもプログラミング教育の実例なのだろうと思われます。
もちろん、こうした新方針が新井紀子氏お一人の提言によるものではなく、新井氏に代表されるような日本のIT/AI専門家と、文科省のお役人の総意として決定されたものだろうと思います。当時の安倍政権のみならず、日本の政治家は与野党ともIT/AI無知ですので、具体的な学習内容などは専門家任せ、お役人任せだったと思います。(*8/15 訂正)
しかしこれらの新しい領域の知識を学んだ子供たちが、自らプログラミングで何かを作り出せるようになるのかといえば、特別に塾などでプログラミングをマスターした子ども以外には、不可能だろうと思います。
発想を逆転すべきです。プログラミング実技と分離された空理論をいくら学んでもプログラムが理解できるはずはありません。ましてや、プログラミングを使って何かを作ることなど起こりえないはず。実際に自分の手を使って実際にプログラミングをする中でしか、プログラミングはマスターできませんし、論理的思考力も養われません。
繰り返し指摘していますが、プログラミングはスポーツと同じです。基本的なルールは机上(座学)でマスターする必要はありますが、その基本的ルールも実技とともにマスターするものですし、技術の進化も深化も、失敗を重ねながら実際に競技をする中でしか獲得できませんし、実現できません。技の進化や深化とは、言うまでもなく、その選手の思考力の進化と深化そのものを意味しています。
ただこのプログラミングを実行するには、その基本設計図に相当するアルゴリズムの知識も必要ですので、アルゴリズムについても基本的な理解は必須ですが、以下三つのアルゴリズム解説記事は、素人にも非常に分かりやすく解説してくれています。
アルゴリズムとは? 意味や使い方、具体例をわかりやすく解説
2023.11.06 スカマン
アルゴリズムって何?意味や種類も解説
シェアマインド経営サークル
アルゴリズムとはどういう意味?具体例やプログラミングへの活用方法を解説
ProgrameiQ
このアルゴリズムの基本設計に従ってプログラミングを書くわけですが、当然のことながら基本的な定型構文(文法)はありますし、プログラミングコードも定型化されていますので、プログラミング言語をいちいち暗記する必要はありません。
初学者はパターン化された構文を使って、アルゴリズム・プログラミングをマスターしていけば、十分に実用的なレベルの技術を習得することは可能だと思います。
ではなぜ新井氏は、プログラミングには数学が必須だと言ったのかといえば、アルゴリズムは数学的な知識・計算式によって導き出されるからです。しかし、定型化された構文を使うのであれば、わざわざ数学を引っ張り出す必要はありません。
ただ、定型構文を変更してさらに処理を高速化したいとか、特別の改変を加えてみたいとかという場合は数学的な知識が必要になってきますが、そうでなければプログラミングの度に数学的な知識まで要求されることはないはず。
にもかかわらず、新井氏がプログラミングには数学が必須だと主張したのは、小中でのプログラミング教育導入反対の根拠を示すためであったと思われます。プログラミング教育反対論は、東ロボプロジェクトの失敗を糊塗するために突如始めた、「プログラミングよりも日本語の読解力を」キャンペーン推進のために考案されたスローガンだったと思われます。それ以外に、新井氏が突如読解力強化運動を始めた理由は考えられません。
実際、東ロボは、始めた時点で大失敗に終わることは明白であったほどに大失敗のプロジェクトであったことは、前号新井紀子批判はなぜ無視されるのかで指摘したとおりです。という結果からも、新井氏はご自分の失敗をうまく糊塗する術を心得た方だとその処世能力の高さにも驚かされます。
3.海外のプログラミング教育
さて、ここで、海外のプログラミング教育事情をご紹介することにいたします。海外と比較することで、日本のプログラミング教育の遅れのみならず、その特異性もさらに際立ってくるはずです。
以下の一覧表は、例示した記事を中心に、過去に拝見したものも含めた多数のサイトを参照してまとめたものですが、各参照記事で紹介国が重なる場合は、より実情に近いと思われる記事を基にしてまとめております。
【学習者必見】海外に学ぶプログラミング教育:日本の現状とこれからの課題も詳しく紹介!
2024年12月12日 WITHCODE
海外のプログラミング教育事情。日本は遅れてる?
2025年2月25日 子プロ
外国(海外)のプログラミング教育事情まとめ│日本は遅れてる?
2025年4月11 SAMURAI ENGINEER
| 国名 | 開始年 | 概要 |
| 日本 | 小学校:2020年 中学校:2021年 |
論理的思考能力の育成のため、特に科目を新たに設けることはしない。 |
| イギリス | 2014年 | Computing教育。5歳からのコンピューティング必修化 ※コンピュタープログラムを書くような実用的な取り組み(*プログラミング教育は企業に委託しているとの記事を読んだ記憶があります。) |
| エストニア | 2012年 | Skypeを発明した国として有名。必修科目ではないがほとんどの学校でプログラミング教育が取り入れられ、ロボット開発の授業などが行われている。 |
| デンマーク | 2014年 | プログラミングを通じて自らのアイディアを形にすることを目指す。 |
| イスラエル | 1990年 | 高校:プログラミング90時間必須、中学:セキュリティやアプリ開発、小学校:プログラミング・デバック。 |
| 韓国 | 2007年 | 2011年からは、イギリス同様のComputing教育が実施されている。高校では、より専門的な内容になり、アルゴリズムやプログラムの設計、プログラマー等の職業に必要な技術などについても学ぶ。ホワイトハッカー養成講座を持つ大学もあり。2025年より、小学校でもAIを学ぶ。 |
| 中国 | 小中学校:2017年 高校:2018年 |
AIを扱える人材の養成を目的としており、AIを扱える人材の養成を目的とし、企業など外部機関の専門家が教えている。プログラミングに関するエデュテック企業も次々に誕生。幼児から大学まで、発達段階に応じたプログラミングアプリも多数開発され、自学自習をサポートする手段も豊富。 |
| オーストラリア | 2015年 | 実践的なスキルの習得を重視し、プログラミングを通じて論理的思考力や問題解決能力を高める。 |
| アメリカ | 2013年 | 州ごとに教育政策が異なるが、カリフォニア州やワシントン州などの先進州では、コンピュータサイエンスを必須化。NPOのCode.orgサイトがプログラミング教育の普及に貢献。オバマ大統領は、STEM(科学・技術・工学・数学の分野を総称する語)教育を重視し、プログラミングを含むコンピュータサイエンス教育を推進(2013年)。 |
| ドイツ | ドイツでは、16連邦州が独自の教育方針を決定するため州によって異なるが、プログラミング教育の導入は3州にとどまる。 | |
| シンガポール | 小学校から大学までの一貫したSTEMカリキュラムを構築。 | |
| インド | 2005年 | 公立学校の3~12年生で、数学の一部に「ICT」と「Computer Science (CS)」教育を開始。「ICT」ではプログラミング、ソフトウェアアプリケーション、インターネットやICT環境の利活用について学ぶ。 |
| ロシア | 2009年 | プログラミング教育は、初等・中等教育では必修科目 |
海外のプログラミング教育を調べるためにいくつものサイトを参照しましたが、保存し忘れたものもあり、ご紹介できない参照サイトもいくつかあります。おそらく、まだ他にもプログラミング教育を導入している国はあるはずですが、一覧にある海外の事例と日本とを比較すると、日本のプログラミング教育の特異性があらためて際立ってきます。両者の違いは、次の4点です。
- 海外ではプログラミング教育の導入が日本よりもかなり早い。
- 海外のプログラミング教育はいずれも、理論と実技が一体化した実践的なもので、プログラミングを通して、論理的思考力や問題解決能力を養うというのが基本姿勢となっています。
- アメリカやドイツなど、州(地方政府)の独立性が強い国ではプログラミング教育の導入にバラつきがあり、全国民に等しく教育の機会を提供することが難しい。アメリカは世界中から優秀な人材が集まってくるので、国としては世界の最先端に位置しているが、個々の国民としては住んでいる場所や貧富の格差などによって、かなり大きな教育格差が存在する。
- 日本は、全国統一的にプログラミング教育を導入しているが、今も全国民がIT/AI無知状態にある、世界でも他に例のない特異性を有している。
日本は2020年にプログラミング教育が開始されましたが、5年経った今も、プログラミング教育を受けてプログラミングに興じる子どもが誕生したという話は見聞きしたことはありません。皆無。全く効果はないということを事実が証明しています。子どもに、実技と分離した、プログラミング理論の基礎となるような知識をバラバラに教えても全く無意味だということです。
例えば、ロボットを使ってプログラミングを学ぶ方が、プログラミングへの総合的な理解とその背後にある理論の真髄にダイレクトに到達できるはずです。実技の中での学びは、頭脳だけではなく感情の動きも含めた全身的な反応を通したものですので、理解は非常に深いものになるはずです。
実はその見事な実例となる子どもロボコン関連記事を、2018年8月に公開したロボカップ2018の後ぐらいに書いて公開した記憶があるのですが、見当たりません。消えています。
正式の名称は忘れましたが、子どもロボコンを主宰するNPOが、ロボットを自作してコンテストに出場する子どもたちの生き生きとした様子をサイトで紹介されていたのですが、想定どおりにロボットを動かすために、子どもたちが様々な工夫を加えることを繰り返しながら、ロボットを動かそうとしている様子には感動を覚えたほどです。
現在検索すると、小学生ロボコンというサイトが出てきます。同じものなのか、後継サイトなのかもしれませんが、以前にはあったNPOの名前がありません。また、ロボコンに参加する子どもたちの様子を、かなり詳しく紹介したページもありません。
YouTube動画はいくつか公開されていますが、コンテストの様子を紹介したもので、目的に沿ったロボットを作る際の、子どもたちの苦労や創意工夫などを語った動画はなさそうです。
以前見たロボコン参加の子どもたちへのインタビュー動画は、コンテストでの優勝を目指して、子どもたちが凝らす創意工夫や修正などのプログラミングを加える手作業を記録したものでした。笑顔いっぱいに生き生きと語る子どもたちの様子からは、論理的思考力は、手と頭と体を使った全身活動として鍛えられることが迫真的に伝わってきました。
残念ながらその動画は見つかりませんが、似たような以下のサイト・動画を発見しました。
ご当地ロボコン(2025年・第4回)
ご当地ロボコン・インタビュー
ご当地ロボコンは今年で4回目とわりと最近始まった催事のようですが、上記インタビューには、子どもたちの生き生きした様子が紹介されています。ロボットを動かすことの楽しさがあふれていますね。
昔見た子どもロボコン(正式名称は忘れましたので取りあえずの名称)サイトには、このような笑顔がはじける子どもへのインタビューが多数紹介されていました。北から南まで、多少の粗密はありながらも、日本全土を覆うように各地でロボコン予選が行われて、各地の優勝チームが本戦で日本一を競うというルールになっていたように記憶しています。福岡市にもありましたね。
中には小学生以下の子どもも参加していて非常に驚いた記憶がありますので、現在の小学生ロボコンよりも年齢制限は緩やかだったのではないかとも思います。現在のご当地ロボコンも小学生という年齢制限はあるようですが、昔の子どもロボコンの雰囲気に近いものを感じます。
ただ目下のところ、北陸地方が中心で全国展開には至っていませんが、元祖ご当地ロボコンとも呼ぶべき以下のロボコンを発見しました。コンテストも今年で9回目。
越前ガニロボコン(2025年・第9回)
おそらく、日本全国をほぼ網羅していた子どもロボコンは、新井氏が、全マスコミの支援を得て強力に推し進めた「プログラミング否定+読解力向上」運動によって異端視され、市民権を剥奪されたのではないか。
越前ガニロボコンは、そんな中で消されずに残った希少な存在だったのではないかとも推測されます。しかもわずかずつとはいえ、北陸全域にその活動が広がりつつあるのは、暗闇に射す一筋の灯りのようにも思われます。燎原の火のようにまでとは行かずとも、この灯りが、徐々にでも日本各地に広がることを願っています。
以上のような事情で、実技を通しての子どもたちのプログラミングの学びの効用をごく一部しかご覧いただくことはできませんが、スポーツと同じだとお考えいただければ、その効用についても即、ご理解いただけるものと思います。
*8/14 追記 なお、プログラミング人材育成のために日本政府が資金援助をしてきた東南アジア各国でも、プログラミング教育は全て実践的なものです。日本に人材を派遣したり、日本に進出してきているのも即戦力になりうる人材がいるからです。*8/14 追記
4.日本のプログラミング教育の特異性
ではなぜ、日本だけが、実践的な力が全く身につかない、世界で唯一例外的に実技と理論を切り離したプログラミング教育が導入されたのか。奇々怪々といわざるをえませんが、その狙いは、結果から考えると一目瞭然。何時までたっても、日本人はプログラミング無知からくるIT/AI無知からは抜け出せない。この状態を望んでいる勢力が存在しているということです。
プログラミングとは、デジタル技術の核心を視覚的に確認できる唯一の手段ですので、その実践的教育を阻害するということは、日本人のデジタル無知を永続させるもっとも有効な手法となります。新井氏はそのことを認識していたか否かは不明ですし、新井氏がそうした勢力とつながっていたかなども不明ですが、新井氏は結果として、プログラミング教育の阻害者としての役割は十二分に果たしたと思います。
では、そうした勢力の働きかけを受け入れたのは誰か。今は亡き安倍総理は、2016年、日本で初めてプログラミング教育の導入を決めましたが、決めた安倍元総理ご自身が、プログラミング教育の目的に反する働きかけを受け入れるとは思われません。そもそも、安倍元総理がそうした勢力とつながっていたのであれば、プログラミング教育の導入を決めるはずはありません。
わたしも銃撃事件以降明らかとなった安倍元総理と統一教会の深いつながりから、統一教会による工作なのかとも思いましたが、もしそうならば、プログラミング教育の導入そのものがなかったはずですので、別ルートからの工作だろうと思い至りました。
そういえば2016年といえば、東ロボプロジェクトを断念した年でしたね。(AIで東大合格断念 「東ロボくん」偏差値伸びず)
(*どこだったか、東ロボに関して書いた記事の中で、2016年は、東ロボプロジェクト開始年と書いた箇所がありますが、開始は2011年で2016年は断念した年でした。*)
前号新井紀子批判はなぜ無視されるのかでは、東ロボに関して新井氏をかなり厳しく批判しましたが、東ロボは、国立情報学研究所(NII)として正式に取り組まれたプロジェクトですので、本来ならば、新井氏批判だけではすまなかったわけです。
しかし、新井氏はプロジェクトのリーダーとして事業を推進されてきましたし、プロジェクト断念後の読解力向上運動でも前面に立って推進なさってきましたので、東ロボ批判=新井紀子批判となるのはやむを得ないと思います。また、名前を出して継続的に批判しているのは全く無名のわたしぐらい。おまけに全マスコミは無批判ですので、わたしの批判ぐらいでは新井氏はほとんどダメージを受けることはないはずですが、日本のマスコミの異様な偏向も不気味そのもの。
そこであらためて問い質(ただ)したいのは、東ロボ断念がなぜ「プログラムよりも読解力向上を!」運動へと転換されたのか、その根拠が全く不明だということです。NIIの事業とすると、この疑問はさらに大きくなるばかり。
おそらく、読解力向上運動という全く場違いともいえる急激な方向転換は、新井氏個人の判断よるところ大だったのではないか。NIIとしても、プロジェクトリーダーであった新井氏の判断に委ねることにしたというのが実情だったのではないかと推測されます。
その後の展開を見ると、プログラミングを否定して読解力向上をという国民的運動は、まさに新井氏個人の事業と化した感ありですね。
この国民的大運動が全マスコミの支援を受けつつ展開されているさ中に、日本初のプログラミング教育の導入が決まり、導入への準備が進められることになったわけですが、プログラミング教育を否定するこの国民的大運動が、プログラミング教育の中身に影響を与えないはずはありません。
事実、日本ではプログラミング教育が始まったものの、実技と完全に切り離された、空理論がバラバラと教えられるだけで、学校教育だけでは誰もプログラミングの「プ」の字の知らないIT/AI無知状態が続くばかりという現実が今なお続いています。
そもそも東ロボプロジェクトは、2021年まで続けられることになっていたという。にもかかわらず、2016年に中断という形で事実上終了したことは、考えれば考えるほど不可解さが募ってきます。偶然なのか意図したものなのかは分かりませんが、「東ロボ中断=プログラミング否定+読解力向上」運動の開始が、プログラミング教育導入時とほぼ同じであったことは、日本のIT/AI教育にとってはこの上もない不運であったことに、あらためて思いを致したいと思います。
時期の一致が偶然だとしても、日本のIT/AI教育にも責任を持つべき立場にあった新井氏の責任は重大であると強調しておきます。
なお、コロナ禍前でしたので、今から7,8年以上前のことになるかと思いますが、わたしは、36Krという中国企業の「今」を紹介するサイトで、中国では、幼児から大学生に至るまでの段階に応じたプログラミングアプリが販売されていることを知って驚くと同時に、日本でもやがてその類似品や日本語版が販売されるだろうと信じて疑いませんでしたが、何時まで経っても販売開始とのニュースはありません。今もなし。
その理由は、新井氏のプログラミング否定論の影響だと思います。当時は新井氏の影響がそこまで大きいとは考えもしていませんでしたが、マスコミをも巻き込む沈黙はそれ以外には考えられませんね。デジタル教育を放棄しつづけてきた歴代政権の責任も重大ですが、新井紀子というスターなしにはここまでの効果はなかったはず。その新井氏を、陰で支えた人物や組織の責任も明らかにすべきだと思いますね。
道州制導入とプログラミング教育の関係
ところで、海外のプログラミング教育を調べる中で、思いがけない事実に遭遇しました。道州制導入運動とIT/AI教育との危険な関係が事実として浮上してきたからです。
一覧にも記載しておりますが、アメリカやドイツなど、州政府の自治権が強い国では、義務教育レベルでのプログラミング教育の導入が遅れているという、これまで誰も指摘したことのない事実が明らかになりました。これらの国では、教育政策も州政府が決定しますので週ごとのバラつきが生じるからです。
アメリカは教育そのものに地域間格差や貧富の格差が反映されていますので、プログラミング教育にも格差が生じてもある意味当然だともいえますが、一方でそのマイナスを補うNPOなどの民間ボランティアの活動も活発ですので、格差がそのまま教育格差につながっているわけではないと思います。
しかしドイツでは、アメリカほどの流動性はないように思われます。わたしはかねてから、AI分野においてドイツの存在感が薄いのはなぜなのかと疑問に思っていましたが、どうやら日本とは違った理由でIT/AIの人材育成が十分には行われていないらしいことが分かり、長年の疑問が氷解しました。
という事実からあらためて維新が主張する道州制の導入を考えると、日本をさらに衰退へと追い落とす非常に危険な政策であることが分かります。
わたしは前号新井紀子批判はなぜ無視されるのかでも、日本国内の政治的な動きから維新が主張する道州制の危険性を指摘しましたが、今回はその批判の正しさが事実として証明されました。前回の道州制批判もそれなりの効果があったのか、あるいは深く潜行して気づかれないように日本解体工作が進められているのかは不明ながら、表立った道州制導入論は鳴りを潜めているように思われますが、今回の海外の実例もとくと参照していただきたい。
5.トランプ関税を悪用する石破総理 *8/11 追記
石破総理は、トランプ関税の交渉結果を記す文書も作成せずに、日本の言い分が受け入れられたと国内向けに喧伝していたものの、大統領令発令で真っ赤なウソであったことが露見。そこでまたもや赤沢大臣が大慌てで9回目の渡米。こんなみっともない対外交渉を繰り返す政権は前代未聞。
赤沢大臣は帰国するや、日本との約束(と保証する客観的な物的証拠はなし)を反映した大統領令が発令されると、今回も文書なしで一方的な思い込みかもしれぬ交渉結果を発表しました。取りすぎた関税は遡って返金するとの合意を得たと主張していますが、この主張を担保する客観的な証拠=文書はなしですので、これも赤沢氏の一方的な思い込みである可能性は大。
「ガキの使いやあらへんで」と言いたくなるようなザマですが、よくもこんな人物が大臣の名前を使ってるなあと呆れるばかり。日本人として恥ずかしいとしか言いようはありませんが、ご本人は恥の意識どころか、得意満面の雰囲気ですね。よほど鈍感なんだろうと思いますね。この点でも石破総理と相似形。
ただ、8日にホワイトハウスは、赤沢氏の言い分を認める簡単な談話を発表したらしいので、何時からかは不明ながらも、15%の上乗せ関税を緩和する特例措置はいずれは実施されるらしい。が、自動車関税は何時から15%になるのかは全く不明。
赤沢氏は今後も、何か齟齬が発生したら渡米することを繰り返すらしい。赤沢氏はおそらく、その都度何か「お土産」を持参してアメリカさまのご機嫌をとるという屈辱外交を屈辱だと感じずに繰り返すのでしょう。
赤沢氏が頻々と訪米しているのは、おそらく秘密裏にトランプ政権の閣僚に賄賂を渡すためだったのではないか。具体的な成果のないまま頻々と訪米していながら、文書一つ作成する段階にまでもっていけないという無能さ丸出しの交渉ぶりは、それ以外に理由は考えられません。
賄賂以外にも、日本の一方的な譲歩貢献策をさらに上乗せする提案をして、トランプ大統領のご機嫌をうかがうという隷従交渉を繰り返してきたのではないか。事実、赤沢氏は、文書を作成しない理由を問われて、日本が譲歩した内容をわざわざ文書に残す必要はないと語っていました。
つまり文書のない曖昧な状況を利用して、実施段階で日本が得になるような状況にしたいということらしいですが、アメリカに対しても失礼極まりない対応です。しかし、仮に曖昧な状況にあったとしても、アメリカが日本の得になるように条件を緩めることは100%ありえません。これは子供にも分かる道理です。
要するに赤沢氏と石破総理は、アメリカに譲歩しすぎたという無能交渉の実態を、石破降ろしが強まる自民党と国民に知られたくない、この無能屈辱的な関税結果は隠しておきたいという思惑から、意図的に文書作成を放棄したということです。
無責任極まりない対応ですが、文書化していたならば、そんな屈辱外交をせずにすんだはずですが、アメリカも「お土産」目当てに、意図的に口約束を反故にして赤沢氏の訪米を待つのではないか。まっとうな国の外交ではありえない、醜態をさらしまくっています。
EUはトランプ大統領と特例措置実施で関税交渉を終えましたが、文書も作成しています。韓国も日本に続いて関税交渉を終えていますが、エネルギーで1000億ドル、投資で3500億ドルで合意していますが、投資はサムスンなどの韓国企業関連の投資だとのことで、韓国内の空洞化を心配して批判の声が高まっているとのこと。
しかし日本の81兆円’・5500億ドルの場合は、日本企業によるアメリカでの投資は全くカウントされず、全て新規の投資やコメを含む農産品の輸入となっています。
韓国は大統領罷免と選挙という大空白がありましたので、対米交渉も超短期間でしたが、日本よりもはるかに有利な条件で合意を得ています。
石破総理は、空白を作るべきではないという口実を使って、民意を無視して総理の座に居座っていますが、関税交渉では頻々と賄賂外交を繰り返すばかりで、長期の政治的空白のあった韓国よりもはるかに悪条件を吞まされています。
国民を欺くために文書作成を放棄するな!といいたい。文書がないと、首相の交代や政権が変わった場合、どうするのですか。石破総理は、政権に居座るために、合意文書を作らせなかったのではないか。こんな政権は前代未聞。外交交渉で文章を作成しないというのは、独裁国家以外には、世界でも例がないのではないか。
*8/11 追記 なお、日本企業によるアメリカでの投資に関して、ソフトバンクの超巨額投資の件について追記します。
日本企業のソフトバンクの孫社長は、データセンターで70兆円、ロボット工場で140兆円という、超異常な投資をアメリカで実施すると派手に発表したものの、実施に向けた動きは全く報道されていません。口先だけの投資話であった可能性もありそうです。
トランプ大統領も孫の超巨大な投資話は信用していない可能性はありますね。日本製鉄のUSスチールへの2兆円投資だけでは、関税ディールに使うには少し規模は小さいとも思われますので、これらがカウントされなかったとしてもやむを得ない面もあります。
となると、孫の大ボラめいたアメリカでの投資話は、日本に対する世界の信用を失墜させただけだともいえそうです。トランプ大統領も騙されたと思っているかもしれませんね。
いや、そうじゃない。実際に投資するんだということであれば、孫社長は即刻、210兆円の投資を具体化すべきではないですか。全く目途もないまま大ボラを吹いただけならば、孫はただただ日本のイメージを悪くしただけです。
しかし、政府に寄生するうま味を知った孫は、石破政権が投資を約束した81兆円を利用して、大ボラの投資話を実行に移すかもしれません。日本政府の投資枠は上限81兆円ですので、210兆円の一部しか充当できないでしょうが、孫が目をつける可能性はありそう。
あるいは、孫は、政府の資金は全く当てにせずに、セックスツールで稼いだ資金を使って、すでにアメリカでデータセンターとロボット工場の建設に着手しているというのであれば、日本企業がアメリカにおいて、超異常な高額投資を始めているにもかかわらず、その超破格の日本企業の貢献を全く考慮に入れない、強欲すぎるトランプ大統領の日本強奪関税を受け入れた石破政権の、異常なまでの無能さが際立つことになりますね。*8/11 追記
********
当初の予定では、プログラミング教育導入の遅れが何をもたらしかについても、海外と比較しながらその実態を具体的に検証するつもりだったのですが、長くなりすぎることとテーマを一つに絞った方がいいと思い、今回はここまでといたします。続きは次号へ。